口の癖(12月下旬)
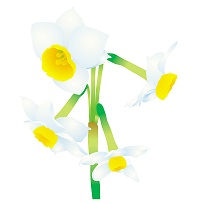
【自分で選ぶ】
先日、あるサイトで「良い口癖」についての記事がありました。
「〜したい!」や「一緒に〜」といった、
相手に好印象を与える口癖の紹介の後、
少し興味深い口癖が出てきました。
「〜しなきゃいけない」を「〜することにした」に
「やらなければいけない」のではなく、
「自ら選んで(決めて)やっている」と認識しなおすことで、
生活の見え方が変わるというのです。
例えば、やらなければならないけど少し億劫な○○の仕事。
まず「○○の仕事をしないといけない」と紙に書きます。
次に「これは自分が選んで○○する事にしたのだ」と考え直し、書き直すというのです。
さらに、「だって〜だから」と、○○をする理由を付け加えます。
「今夜、アメリカ人と英会話をしなきゃいけない」を、
「私が選んで英会話をすることにしたのです。だって英会話の力を身につけられるし」に。
なんだか元気が出てきます。
……時には「ぼやく」のも大事かもしれませんが。
【お迎え】
口癖を変えてほしいなと思う時があります。
80代をすぎた一人暮らしの女性の口癖です。
一緒にお勤めをしてお茶を飲みながら、
その方はよくおっしゃいます。
「毎日疲れます。もう早く“お迎え”がきてくだされば。」
愚痴を聞いてもらいたいのかもしれません。
でも何度も言われると、冗談で言い返したくなります。
「お迎えって、タクシーですか?」
ここでの「お迎え」とは何か。
臨終に、阿弥陀仏が浄土に導くため迎えに来ることです。
「冥土からお迎えが来る」と言ったりします。
浄土真宗のご本尊は阿弥陀さまですが、
臨終のお迎えの有無には全く用事がありません。
他力のお念仏をいただくお互いです。
「阿弥陀さまは臨終になってやってこられるのではなく、
いつもいらっしゃっておられました」と気づく時、
「はやくお迎えが……」、
その口癖は自然と消えるかもしれません。
【片足】
また70代をすぎた男性です。
「もういつの間にかこんな歳になってしまった。もう片足が入っとるわい。」
愚痴を聞いてもらいたいのかもしれません。
でも何度も言われると、冗談で言い返したくなります。
「入ってるって、お風呂ですか?」
この「片足が入っている」とは何か。
「棺桶に片足(だけ)入っている」という慣用句の事です。
わが身の老いを思い、もうすぐ死んで、火葬される事を意味します。
浄土真宗は信心をいただく時、
片足どころか両足全て、完全に阿弥陀さまのお慈悲の湯船につかっています。
その気持ち良さ(ご恩報謝)から「南無阿弥陀仏」と声が出るのです。
【死もまた】
今年ご往生された若林真人先生が、
かつて山本仏骨先生の晩年の口癖を紹介くださいました。
それは「死もまためでたし」。
み教えをお聞かせにあずかる時、
死は敗北でも、消滅でも、絶望でもありませんでした。
弥陀の本願のはたらき通り、
お浄土で仏と成らせていただく人生は、
尊い人生、めでたき人生です。
ではそんな晩年は苦しくないかというと、そうではありません。
では何が違うのか。
「(山本)先生、苦しいですか。」
「ああ、人間の器をさずかってるからね。」
病気の痛みにこらえながらも、
「苦しみを眺めていける人生」がひらけます。
お釈迦様のお示し通り、
四苦八苦のままならない人生です。
老いの苦しみ、病の苦しみ、死の苦しみ。
その苦悩の私を救う仏さまは、
いつでもどこでも来てくださっています。
苦難のまっただ中であっても、
そこは法のはたらいている現場です。
どっぷり両足を入れた本願の法という温泉場です。
「なぜこんなに苦しまなければならないのか」という思い。
お法(みのり)にであい、思い直してください。
「自業自得。自分で選び生み出した苦しみの人生です。
だって仏の話を聞かないといけない私でしたから。
そしておかげで仏のお慈悲にあうことができました。」
物の見方が変わり、
愚痴がこぼれる口癖から、
お念仏こぼれる口癖へ。
大きな人生の味方になります。
(おわり)
