�ڎ��F
- 12�����{
- 12����{�u���т����鑤�̌��t�v
- 11�����{�u�n�ƈ�Ɂv
- 11����{�u�����Ɂv
- 10�����{�u�H���ƕ����v
- 10����{[�p�����́v
- 9�����{�u�����̖ړI�v
- 9����{�u��C���킹�v
- 8�����{�u�O���̊́v
- 8����{�u������v
- 7�����{�u���ꂸ�E�������v
- 7����{�u�肢�ɐ�����v
- 6�����{�u���ɐ�����v
- 6����{�u�Y�����́E�Y��Ȃ�����
- 5�����{�u���ւ̂��Ƃ��v
- 5����{�u���w�����v
- 4�����{�u��̂���Ɓv
- 4����{�u�֑��̂Ȃ������v
- 3�����{�u�^�@�̌ւ�v
- 3����{�u����������Ȃ��v
- 2�����{�u�@���̌��v
- 2����{�u���@��̎��v
- 1�����{�u������v
- 1����{�u���݂̂�Ɂ@�݂݂����܂��v
���т����鑤�̌��t
�y���݂��̌��t�Ɂz
���N��3���A���郉�W�I�ԑg�ŁA
�u�ۋ��v�Ƃ������t���b��ɏオ��܂����B
�ۋ��Ƃ͖{���u�����ۂ���v�Ƃ������t�ł��B
����Ď����ɂ͑�́u�g�p�܂��͗��p�������ۂ����A�܂����̗����v�Ƃ���܂��B
�u���ԉۋ����v�Ƃ��������́u�ۋ��v�����̈Ӗ��ł��B
�Ƃ��낪���s���l�Ɂu�ۋ��v�̈Ӗ���������Ă��炤�ƁA
�u�������̂��ޏ�Ԃ��߂����Ă����������ލs�ׁv
�u�D���Ȃ��̂ɂ����������邱�Ɓv
�u�y�����Ƃɂ������Ă������͂炤���Ɓv
�u�����ł͂ł��Ȃ����̂ɂ����������ނ��Ɓv
�u�������g���ĉ��������炤���́v
�܂藿�����ۂ���i���킹��E��������j���Ǝґ��̌��t�ł͂Ȃ��A
�������ۂ���ꂽ�i�x�����E�����ɉ�����j���p�ґ��̌��t���C���[�W����̂ł��B
�����̓X�}�z�̕��y�ł��B
�u�A�C�e���ɉۋ�����B�v
�u�����ɉۋ�����B�v
�̂͂Ȃ��������t�ł��B
�{���͌�p���������̂����y�������蒅�����̂ł����B
����Ƃ悭�����Ⴊ�u����v�ł��B
�����ʂ�ɂ����u������v�ł�����A�u��t�����Ăт����邱�ƁB��j��������v�ł������A
���ł́u��������t���邱�ƁA�܂����̂����v�ɂ��g���܂��B
����ɂ����u�݂���v�B
�u���X��݂����ĖY�N������܂����B�v
�{���͎�鑤�̕��́u���v�Ƃ����ׂ��ł��傤���u�݂���v�ɁB
�u���X��݂���܂���v�ƌĂт����鑤�̌��t���A
���݂́A�����鑤�̌��t�g���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�y�����̒����z
���́u�ۋ��v��u����v�̌��t�g���̕ϗe�Ŏv���̂��A
�e�a���l�̂����t�ł��B
�����������āu�A���v�͖{�菵���̒����Ȃ�B�i�s���j
�u�얳����ɕ��v�����߂����ꕶ�ł��B
�u�얳����ɕ��i�Ȃ����݂��Ԃj�v�̓C���h�̌��t�ł��B
�����āu�얳�v�͑f���ɖƁu�A�ːM���v�u�A���v�Ƃ������Ӗ��ŁA
�u�S����M���h���v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�u����ɂ��܂�S����M���h���܂��B�v
�܂莄�����̑��̌��t�ł����A
�e�a���l�͂����āu�{�菵���̒����v�A
�����܂̊肢�ɂ���u���̂܂ܗ�����A�K���~���v�ƕ����܂��������Ԃ����t�A
�܂蕧�A����ɂ��ܑ��̌��t�Ŏ߂���܂��B
���O���͍ŏI�I�Ɏ����O���A���ɏo���s�ׂł��B
����������͎����������w�сA�q�d���݂����A�������[�����āA�M���ď̂���A
���̂悤�ȗނ̂��̂ł͂Ȃ��̂ł��B
�O�i�K�ɕ����ܑ��́u�Ăт����v������܂��B
�q�d�ǂ��납�ϔY�܂݂�A
�~���悤�̂Ȃ����̖{�����������A
����ǂ�����Ȏ����~�������Ɗ肢����������܂��B
���̊肢�̒ʂ�̕��A�����ƂȂ��Ă̂͂��炫���i�O�i�K�Ƃ��āj����̂ł��B
�u���ɂ܂�����v�u�K��������v�Ƃ̕����ܑ��̌Ăт����ɁA
���������̍s�ׂ��u�얳����ɕ��v�A
�u���܂������܂��v�u������܂����v�Ƃ������O���A
�������O���A���O�ł��B
�ɂ�炢����
�킽�����@�������ā@�������ā@�������ā@�������ā@��������̂�
���˂�Ԃ\�\
�ɂ�炢����̂�������
�킽���Ɂ@�Ƃ����ā@�Ƃ����ā@�Ƃ����ā@�Ƃ����ā@�������ꂽ�̂�
���˂�Ԃ\�\
�i�w�O�������x146�Łj
���O���͕����ʂ�ɂ����u�����i�����j�O����v�̂ł����A
����Ӗ��A�u�����i�����j�O����v�Ăт����ɉ��������t�Ȃ̂ł��B
�y���͖{��̌�p�z
�����ꌾ�B
�����̌��t�Ō�p����蒅��������̂Ƃ����u���͖{��v�B
��y�^�@�ő�ɂ��錾�t�ł��B
����́u���͖{���M���v�Ƃ����悤�ɁA
�u����ɔ@���̖{��̂͂��炫�v�A���Ȃ킿�����ܑ��̌��t�ł��B
�������ƂȂӂƂ��ӂƂ��A���͖{���M�������͕Ӓn�ɐ��܂�ׂ��B
�{�葼�͂��ӂ����M����Ƃ�����́A�Ȃɂ��Ƃɂ��͕Ӓn�̉����ɂČ�ӂׂ��B
���̂₤���悭�悭�䂱���낦�Č�O����ӂׂ��B
�i[�a��]�@���ǁA�������̂���Ƃ����Ă��A
�{�葼�͂�M���Ȃ��悤�Ȃ�Ӓn�i����y�̂������݂̂悤�ȏꏊ�j�ɐ��܂�邱�Ƃł��傤�B
�������{�葼�͂�[���M����l���A�ǂ����ĕӒn�ɉ�������悤�Ȃ��ƂɂȂ�ł��傤���B
���̂��Ƃ��悭�S���āA�O�����Ȃ���Ȃ�܂���B�j
�i�e�a���l������@��26�ʁA�w���ߔŁx785�Łj
����ǂ������A����Ȏg���������ɂ��܂��B
�u�������͖{��ł��������Ȃ��B�v
���̏ꍇ�A�u���͖{��v�͕����ł͂Ȃ��A�}�v�̎������̌��t�ƂȂ��Ă��܂��B
���́A���̏ꍇ�́u���͖{��v�́A
�u�ۋ��v�u����v�̂悤�ɁA�P�Ɂu�Ăъ|���鑤���牞���鑤�̌��t�g���v�ɂȂ��������łȂ��A
���e�܂ŕς���Ă��܂��Ă��܂��B
�u�������͖{��ł��������Ȃ��v�Ƃ������{�l�B
�u��������ɕ��̑��͖{���M���邵���Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă͂��܂���B
������u�^��V�ɂ��܂����邵���Ȃ��v�A
�u���̋��n���ǂ��������Ăق����v�Ƃ����Ӗ������ł��傤�B
����ɂ��܂̍��{�̊肢�ł���u�{��v���A���̐l�̐Ȃ�肢�ɂȂ��Ă��܂��B
�u�ߊ�B���v�Ƃ������ꍇ�́u�ߊ�v�Ɠ��l�ł��B
�ߊ�́u��߂̊肢�v�ŁA����������܂̊肢�Ȃ̂ł����B
���́u�^�܂����v�ɂȂ��Ă���u���͖{��v�̌�p�B
��y�^�@�̋����Ɛ[���ւ���Ă��邾���ɁA
���̌�p���������Ӗ��ɂȂ鎖�́A�����������̂ł��B
�i�����j ���`����
�n�ƈ��
�y�P�Q���̓��j���z
���N���O�̂����V�ł����B
�̐l�͑r��̉�����B
�����V���I���A
����l�Ƃ��̎q�ǂ������v�w�ł��������Ȃ���A
�S�X����̖����A�@�v�̓����𑊒k���܂����B
���낢�둊�k�������ʁA
�����̒��j����̓s���łP�Q�����{�̓��j���Ɍ��܂肻���ɂȂ������A
�ˑR���j�̂g�������o���܂����B
�u�����A���̓��́I�v
�u�ǂ������A�s���������̂��H�v
�u����A�Z���s���������Ȃ炻�̓��ł�����B�v
�u�ǂ������́H�@��������Ȃ炢���Ȃ�����B�v
�u����A������A������c�c�v
����Z�킪���x�������˂܂����B
�����Œ킳��͌����܂����B
�u���́c�c���̓��͗L�n�L�O�������ł��B�v
�ꓯ����B
��Œm�����̂ł����A
�����̋��n�D���̕��ł����B
�g����͌����܂����B
�u�S������v���āi�ϐ�́j������߂܂��B�v
�y�����z
�u������v��u�O����v���A�����́u���ށv�Ƃ����Ӗ��́u���v�Ƃ�������p���܂��B
�u���v��s�g�Ȏ��Ƃ��Ċ������i��������j�̂ł͂���܂���B
�u�����݁v�i���̂̒m��Ȃ����̂���������j�̂��߂̋V���ł�����܂���B
���Ԃ̖��������������āA���@�̂����ɂ����܂��傤�Ƃ����̂���y�^�@�́u���ށv�ł��B
���Ƃ��ӕ����̌P�͂��݂Ȃ�B���ꂷ�Ȃ킿���̖S���ɂ����āA
���̓����ӂ�����ق��ɑ��������݂ċ֒f����`�Ȃ�B
�w������x�i�w��y�^�@���T�S���x4���A1361�Łj
���̐l���v������ɂ��A���̐l������Ă��鎖�Ƃ��āA���g�����@�i�݂̂�j�ɂł����̂ł��B
�얳����ɕ��̘b�A
���Ȃ킿����ɔ@���̂��b�A
�{�萬�A�̖����Ƒ��͉���̌����̘b���܂��B
����͑��Ȃ�ʎ��̘b�ł��B
�ǂ��܂ł����ʎ���|��A�킪�߂��߂Ƃ��v���ʎ��̂��߂̘b�B
���������ł���A���ꂩ��������ʔϔY�ߑ��̖}�v�̎����~���Ƃ������@�̘b�ł��B
���̒��S�͔@���̂��{��ł���A
���̖{�͖̂����i�{�萬�A�̑��j�A�u��و���ɕ��v�ɂ���܂��B
�����u��و���ɕ��v�������̂��A���̂͂��炫�ɂ��܂������A��y�̐��E�������������B
����Ȏ��̍s���E�S���̌��́A�ǂ��܂ł��@���̂ЂƂ���炫�A�����̂͂��炫�ł��B
��H�̎��̎��͂̐S�i������ς܂�Ƃ���S�j�ł����A�@���̋~�ςɂ͕K�v�łȂ��A
�ނ���ꗱ�̎��͂̐S�i�@�����^���S�j�����A�~���̎ז��ɂȂ�̂ł��B
�@���̂͂��炫��Ƃ��������A
�킪�g�́u���̂����̂��̖̂��v���������ɕs���Ȃ��g�ƂȂ����S�Ԃ�A
������u���͂̐M�S�v�Ƃ����܂��B
�y���}��́z
���݁A���j���ɋ��n���ނɂ����h���}����������Ă��܂��B
�ȕv�ؑ��剉�́u���C�����t�@�~���[�v�B
�L�n�L�O�ł̗D����ڎw�����h���}�̂悤�ł��B
���̑��b�ł���ȑ䎌���łĂ��܂����B
�����ł��i���n�Łj�������グ�����Ȃ�A�����̂����n���������Ă����B
�ł��ȁA�����̂����n�����������邽�߂ɂ́A����ȃJ�l���v���B
�ł��A���n�͂��ꂾ������˂��B
�ςJ�l�̊z���������s�����߂�킯����Ȃ��B
������ȁA�ق�̈�u�A�n�ƃW���b�L�[���A����A�n�Ɋւ�邷�ׂĂ̐l�Ԃ��A�n�ƈ�̂ɂȂ�u�Ԃ������B
�܂����l�n������Ă���B
���ꂪ���ׂĂ��Ђ�����Ԃ����Ƃ����Ă���B�����m�����܂�����A������߂��Ȃ���B
�l�n��́A���̏u�Ԃ��ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��A
���n�����Ȃ����ɂ͕�����܂���B
���n�D���̂g����ɂ͕�����̂�������܂��B
�l�n��͕̂�����܂��A
���͂̐M�S�����������������u���}��́i�Ԃڂ������j�v�Ƃ����܂��B
���S�Ɩ}�S���܂�������ɂȂ��������ł��B
�}�v�̔ϔY�̐S�̑S�̂ɕ��S��������Ƃǂ��܂��B
�ϔY��̖}�v����y�ŕ��ɂȂ�ׂ��g�ƂȂ炵�߂�ꂽ��Ԃł��B
�S����ϔY���������킯�ł͂���܂���B
�@�����܂ƈ�ɂȂ��Ă���l���ł��B
���傤�ǐ삪�C�ɓ��荞��ŁA���ׂĒ��ɂȂ�����Ԃł��B
��̐����������킯�ł͂���܂���B
������������̐��͂���܂���B
��̐����]����꒪�ɐ�������ԁB
����ȓ]���i�Ă傤�j�̐S�����Ȃ�����O���҂ł��B
������u�]�����P�̉v�i�Ă�܂����傤����̂₭�j�v�Ƃ����A
���͂̐M�S���������������v�̈�Ɛe�a���l�͎�����܂��B
���肦�Ȃ��������Ȃ��Ƃ���ꂽ��ԁB
�u�����m�����܂�����A������߂��Ȃ���B�v
�u��و���ɕ��v�ƕ̂��O���������ɂ͂��������Ȃ������̈���ł��B
�i�����j ���`����
������
�y�ԈႢ�������z
�ˑR�ł������ł��B
���̕��͂́A��y�^�@�ő�ɂ��Ă���u�̉v�ł��B
�����̎���������킵�Ă��܂��B
�܂��͐��ɏo���ēǂ�ł݂Ă��������B
�@�@���������G�s�G�C�����̂�������ӂ肷�ĂāA��S������ɔ@���A���炪���x����厖���㐶�A�������������炦�Ƃ��݂̂������Ă����낤�B
�@�@���̂���O�̂Ƃ��A������� �������������Ƃ��A���̂������̖��́A��������Ƃ��A��낱�т����������낤�B
�B�@���������Ƃ�������������킯�����낤���ƁA���J�R���l���o���̂����A �����������P�m���̂������炴�邲�����̂����ƁA���肪�����������낤�B
�C�@���̂����͂����߂������������|�A�����������A�܂���������ׂ������낤�B
�ǂ�ł݂܂������H
�ł͖��ł��B
���̕��͂́u�̉v�Ƃ悭���Ă��܂����A
�ԈႢ���R�ӏ�����܂��B
�S���Ӗ��̈قȂ錾�t�i�n��j�ɕς���Ă��܂��B
������܂����H
�@�@���������G�s�G�C�����̂�������ӂ肷�ĂāA��S������ɔ@���A���炪���x����厖�������A�������������炦�Ƃ��݂̂������Ă����낤�B
�@�@���̂���O�̂Ƃ��A������� �������������Ƃ��A���̂������̖��́A��������Ƃ��A��낱�т����������낤�B
�B�@���������Ƃ�������������킯�����낤���ƁA���J�R���l���o���̂����A �������������m���̂������炴�邲�����̂����ƁA���肪�����������낤�B
�C�@���̂����͂����߂������������|�A�����������A�܂���������ׂ������낤�B
�����͂��̖@�b�̍Ō�ɂ���܂��B
�ʔ��������ł��傤���H
�u����Ȃ̊ȒP������B�v
�Ƃ�������������ƂĂ��������v���܂��B
�ł͖@�b���n�߂܂��B
�y�������z
���N�̉ċx�݁A���w�Q�N�̎��j�́u�E��̌��v�ɍs���܂����B
�s������͏����Ȃ̕a�@�ł����B
�Q���ԁA�l�X�ȑ̌��������Ă�����������ł��B
�̌����Ԓ��A���q�͏����Ȃ̐搶�Ɏ��₵�������ł��B
�u�搶�͎d�����A������ԑ�ɂ��Ă��܂����H�v
����Ɛ搶�́A�u�����ł��邱�Ɓv�Ɠ������܂����B
���Ƃ��Ί��҂̎q���ɒ��˂�����Ƃ��A
�������Ԏq���Ɂu�ɂ��Ȃ�����ˁv�Ƃ͌����܂���B
�E�\�͌��킸�ɁA
�����ɑΉ����A�a�C���������Ƃɂ���āA
�q�ǂ������Ƃ̐M���W���������̂������ł��B
�m���������ł��B
�⑰���߂��ޑ��V�ł����A
�u�̐l�͂���y�ɂ�����܂�����v�Ƃ��������́A
���ՂɌ���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B
�Ȃ��Ȃ�A
���̕�������y�ւ܂�����i���ˁj�ł���u���͂̐M�S�v�����������Ă������ǂ����A
������Ȃ�����ł��B
����������͈̂�B
���A���V�Ƃ��������̂������u�����v���������Ă��鎖���ł��B
�������A���T�̌��t��ʂ��āA
�@�����܂̂����������Ă��������܂��B
���Ƃ͐^�t�̓�����ށA�ɏd���l�̎����A
�����ė����Ȃ������A����ɔ@���̂����߂��܂��B
����ȑ�Ȏ��̕������A���̐l�����V��ʂ��Č���ł��������Ă��܂��B
�y�h���ʂꂾ���z
�����͂����Ă����V�̌���͂炢���̂�����܂��B
�N���������Ȃ��犻�ɉԂ�������܂��B
�u�����ł��Ȃ��������B�v
�����̏�킫�������Ă��܂��B
�u�̐l�ɉ����ł��邱�Ƃ́H�v
����Ȏv����������̂����ɂ����Ƃ��ł��B
�Ȃ�A���̔߂��݂������ɕ��@������̂���y�^�@�ł��B
��蓹�ɂ݂��邩������܂��A
�����ɂ͊m���ȓ���������܂��B
�����N�����́A�w�V�ُ��x����i���P�j�̂��@�b�̒��ŁA
���̂悤�Ȃ��b������Ă��܂��B
�{���̂��Ƃ͂킩��Ȃ���
�u���܂�Ă��Ă����ɖS���Ȃ����䂪�q�͂���y�ɎQ�����̂ł��傤���v�Ƃ���������邱�Ƃ�����܂��B����͑m���Ƃ��ē������Ȃ����ł��B�Ƃ����̂͑m���ɂ��{���̂��Ƃ͂킩��܂���B��Ƃ��ẮA�u�ǂ�ȕ��ł�����y�ɎQ�����v�ƌ��������̂ł����A��������Αm�����g���A�u�����s�v�_�v���f���Ă��邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂��B
�@���́u���������v�̖����������������Ă��炦�A��̓���������܂��B��͂��́w�V�ُ��x�̂����t�ł��B�u���Ȃ��̂��q������y�ɎQ��ꂽ���ǂ����́A���Ȃ�������y�ɎQ��킩��܂��B��������y�ʼn�Ȃ���i�~���Ă��Ȃ���j�A���ƂȂ������Ȃ����~���Ă������܂���v�Ƃ������̂ł��B
�@������̓����́A�u���Ȃ��̂��q����́A���Ȃ��ɂ��̐��̖����m�点�ĉ����邽�߂ɂ��̐��Ɍ���Ă�����F���܁A�P�m���i����������j���܂�������܂���v�Ƃ������̂ł��B
�@�������A������̍l��������܂��B����́A�u��y�^�@�͈���ɂ��܂ɂ��܂�������@���ł�����A���̌㐶���@�����܂ɂ��܂������܂��B���̉Ƒ��̍s����������ɂ��܂ɂ��܂������܂��v�Ƃ����̂��{���ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ƃ����̂́A�@�����܂͍����ꐶ��������ɂ��Ă���̂ł͂���܂���B�u���Ƃ������A�����Ȃ��Ă��A�����ł͕K����������ł��̂��̂��~����v�Ƃ�������鈢��ɂ��܂ɁA�Ƒ��̌㐶�̂��Ƃ����܂���������̂��A��y�^�@�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i�����N���w����Ȃ番����V�ُ��x�u��R�P��@�����Ƒ��̌㐶������ɂ��܂ɂ��܂����v�A150-151�Łj
���e�Ƃ̕ʂ�̒ɂ݂́A�����Y�ꋎ�肽����������܂���B
�������m���́A
�u���v�ł���B���̕��͂�������y�ł���v�Ƃ͌����܂���B
�������ł����A���̒ɂ݂������ɁA
�����ňꏏ�ɂ������������܂��B
�����āu������肾�����v�ƋC�Â�����A
�����āu���̂���y�̘b�͎��̂��߂ł����v�Ƃ��������܂��B
���������������鑊��ɂł������A
�����̉������܂�A
��y��������܂鎖�A
���̎������̂܂܁A�ʂ�̒ɂ݂̉����Ƃ��Ȃ�̂ł��B
�y�ԈႢ�T���̓����z
�@�@���������G�s�G�C�����̂�������ӂ肷�ĂāA��S������ɔ@���A���炪���x����厖�������A�������������炦�Ƃ��݂̂������Ă����낤�B
�@�@���̂���O�̂Ƃ��A������� �������������Ƃ��A���̂������̖��́A��������Ƃ��A��낱�т����������낤�B
�B�@���������Ƃ�������������킯�����낤���ƁA���J�R���l���o���̂����A �������������m���̂������炴�邲�����̂����ƁA���肪�����������낤�B
�C�@���̂����͂����߂������������|�A�����������A�܂���������ׂ������낤�B
- ���͂̂�������ӂ肷�Ăāc�c�����܂̘b���u���l�C���v�ƕ����Ԉ���Ă���\��������܂��B
- �����̈�厖�c�c�u����Ȃ�舢��ɂ��܁A�����Ƃ����Ă��������v�Ǝv�������܂�A�����܂̂��b�i�肢�j�����ɓ����Ă��Ȃ���������܂���B
- ���m���c�c���Ƃ��u���̘b�Ȃ�Ă����Ɠ�����A���������B������ꏏ�ɉf��ɂł��s���܂��傤�v�Ƃ����l�B
�i���P�j
�w�V�ُ��x��T���Ƃ͎��̂悤�ȕ��͂ł��B
�u��@�e�a�͕���̍F�{�̂��߂ƂāA��ԂɂĂ��O���\�����邱�ƁA���܂���͂��B
���̂��́A��̗L��݂͂Ȃ��Đ��X���X�̕���E�Z��Ȃ�B
���Â�����Â���A���̏������ɕ��ɐ���Ă�������ӂׂ��Ȃ�B
�킪������ɂĂ͂��ޑP�ɂĂ���͂����A�O����������ĕ��������������͂߁B
�������͂����ĂāA��������y�̂��Ƃ���Ђ炫�ȂA�Z���E�l���̂��Ђ��A���Â�̋Ƌ�ɂ��Â߂�Ƃ��A�_�ʕ��ւ����āA�܂×L����x���ׂ��Ȃ�Ɓm�]�X�n�B
�i������
�e�a�͖S������̒ǑP���{�̂��߂ɔO���������Ƃͤ ���Ĉ�x������܂����B
�Ƃ����̂ͤ ���̂�����̂͂��ׂĂ݂Ȥ ����܂ʼn��x�ƂȂ�����ς莀�ɕς肵�Ă������Ť ����ł���Z��E�o���ł������̂ł�� ���̐��̖����I��� ��y�ɉ������Ă������ɕ��ƂȂ� �ǂ̐l�����݂ȋ~��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��
�O���������̗͂œw�߂�P�ł���܂��Ȃ� ���̌����ɂ���ĖS��������~�������܂��傤��� �O���͂��̂悤�Ȃ��̂ł͂���܂���
���͂ɂƂ��ꂽ�S���̂Ĥ ���₩�ɏ�y�ɉ������Ă��Ƃ���J�����Ȃ� �����̐��E�ɂ��܂��܂Ȑ���� �ǂ̂悤�ȋꂵ�݂̒��ɂ��낤�Ƃ� ���R���݂ŕs�v�c�Ȃ͂��炫�ɂ�� �������܂����̂���l�X���~�����Ƃ��ł����̂ł��
���̂悤�ɐ��l�͋��ɂȂ�܂�����j
�i�����j ���`����
�H���ƕ���
�y�J���C�z
��N�ʑO�A�u��l���ނ������̂ŁA�ǂ����v�ƁA
��������������Ձi�J���C�j�������Ă����܂����B
�r�j�[���܂����ƁA�܂������܂����B
�u�����Ă܂��H�v
�u�����A���̂܂ܗ①�ɂɂ���Ė��Ȃ��ł���B�v
����ꂽ�Ƃ���A�①�ɂɓ���܂����B
1���Ԍ�A���C�Ȃ��①�ɂ��J���܂����B
�ڂ̑O�ɂ̓J���C�̓������r�j�[���܁B
���ƂȂ����̈ʒu����قǂƂ͈Ⴂ�܂��B
�u�����A�����Ă�̂��B�v
���ꂩ��܂�1���ԁB
���ݕ����Ƃ낤�Ƃӂ����ї①�ɂ��J���܂����B
����ƃr�j�[���܂���яo���Ă��܂����B
�ǂ����J���C���������̂ł��傤�B
�r�j�[���܂��ړ����āA
������̕������①�ɂ̔��̃|�P�b�g�̉����ɂЂ��������Ă����悤�ł��B
�������͂��݂ŁA
�r�j�[���܂��獕�₩�ȃJ���C���j���b�Ɣ�яo���Ă��܂����B
�v���Ԃ�ɐ⋩���܂����B
����������G���������Ȃ����B
�ǂ�������ǂ��������ӂ����Ă���ƁA
��e������Ă��܂����B
���̎�����������ƁA�u�܂��܂��v�ƌ����Ȃ���A
�������ƃJ���C�����݁A
�u�悵�悵�v�ƌ����Ȃ��琅�B
�M�ɂ̂��ă��b�v�����ė①�ɂɓ���Ă��܂��܂����B
�v���Ԃ�ɐe�h���܂����B
�y�H�ו��͐������z
�v���o�����̂��A
��N�S���Ȃ�ꂽ�r�搶�̂��@�b�̂��Ƃ��b�B
�e�q3�㋛�ނ�̓��������^�R��ނ���
�r�搶�̂����Ɏ����Ă����܂����B
�����������͋C�ɂ����①�ɂɓ���܂����B
���̒��B
�����①�ɂ��J���悤�Ƃ���Ƃ����܂���B
���������������Ă�悤�Ȃ̂ŁA
�͈�t�A������������܂����B
����Ƃ����ɂ͑傫�ȃ^�R���ւ���Ă��������ł��B
�ڂ̑O�̑�_�R�ɁA������͐⋩���ꂽ�����ł��B
�c�c
�①�ɂ��J���܂��B
�n���◑�A�h�g��ώρc�c�B
�����܂��A
�u�H�ו��͐������v�ł��B
�y�ꗱ�̗܁z
�u�����v�@�@�@�@�@���q�݂��U
�@�@�C�̋��͂��킢�����B
�@�@���Ă͐l�ɂ�����A
�@�@���͖q��ł����Ă�A
�@�@���������r�łӂ����炤�B
�@�@����ǂ��C�̂�����
�@�@�Ȃ�ɂ����b�ɂȂ�Ȃ���
�@�@�����������Ȃ��̂�
�@�@�������Ă킽���ɐH�ׂ���B
�@�@�ق�Ƃɋ��͂��킢�����B
�������͐H�ׂ��ɂ͐����Ă����܂���B
����͌���������ƁA���̂��̂��́A
���̐������̂��̂��̋]���̏�łȂ肽���Ă��܂��B
���q�݂��U�́u�����v��u�務�v�͂��̎����������Ă��܂��B
�����Ă���̂ł͂Ȃ��A��������Ă��鎩���ɋC�Â�����܂��B
�J��r���Y����ɂ����̎�������܂��B
�����̋�
�@�@�������Ȃ����Ȃ͂������Ȃ�����
�@�@���イ���炢�̂����Ȃ�����
�@�@���イ���炢�̂����Ȃ�
�@�@�������Ȃ����Ȃ�����
�@�@�������Ȃ����Ȃ�
�@�@�����Ƃ�������
�@�@�����Ȃ�����
�@�@���̂��͂��̂��������ɂ��Ƃ���
�@�@�Ђ��肩���₭
�@�@�����킹�͂ӂ����킹���₵�Ȃ��Ƃ���
�@�@�͂ȂЂ炭
�@�@�ǂ�Ȃ�낱�т̂ӂ������݂ɂ�
�@�@�ЂƂԂ̂Ȃ݂���
�@�@�Ƃ��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ�
�@�@�@�@�@�i�w�N���[�̊G�{�x���j
��������������w����A
�O�P�W�̍����g�ȁw�N���[�̊G�{�x�Œm��܂����B
���̖��������тɂ��A
�ڂɌ����Ȃ��܂��n���Ă��܂��B
�y���������܁z
�����̂��̂��Ƃ݂Ȃ��܂̂������ɂ��
���̂����������߂��܂�܂����B
�[�����������
���肪�������������܂�
��y�^�@�{�莛�h�́u�H�O�̌��t�v�ł��B
��������G�l���M�[�����������ڂ̑O�̐H���́A
�����̂��̂��̏�ɁA
�����Ă�������̕��X�̂����ɂ���Đ����܂����B
���̎����u�Y�ꂸ�v�ɂ��������܂��B
����ǂ�������B
��y�^�@�́u�Y����Ă��Ȃ��v����Y��Ȃ��̂ł��B
���Ȃ킿����ɂ��܂�����Y��Ă����Ȃ����B
���ڂłȂ��ɂ���A�����H��������Ƃ������́A
�E���̍s�ׂȂ����Đ������܂���B
����ȍߋƂ̎����~���̑���ƌ����ĖY��Ȃ������܂��A
����ɔ@���Ƃ������{������Ă������܁B
���Ǝ����̓����ŁA���Ԓn���ɗ����䂭�����A
�Y�ꂸ�������A�������و���ɕ��̖����ɂ��߂Ăӂ�ނ��Ă����܂��B
����������́u���������܁v�ł��B
�H���������ɕ��������������܂��B
�H�~�̏H������Ă��܂����B
�����A�����̂��̂������������A
�����̕��X�Ɋ��ӂ��A
�傫�ȕ����𖡂키���ł��B
�i�����j ���`����
�p������
�u�������푈�Ȃ�Ă���킯�Ȃ��B����Ȃ̂܂₩�����B
�܂₩���̐��`�̂��߂ɁA�G���������A���Ԃ��吨���B��q���c
�i�����j
������A���`�ȂM�����Ⴂ���Ȃ��B
����Ȃ��̊ȒP�ɂЂ�����Ԃ����B
�ł��A�����t�]���Ȃ����`������Ƃ�����c�c�S�Ă̐l������鐳�`�B
�l�͂�������������B
�i�����j
���N�������Ă��A���\�N�������Ă��A�݂�Ȃ���������B�v
�i���h���u�A���p���v���j
��1
�y�����Q��̈Ӗ��z
��������̎����Q��ł��܂ɂ��������A
���Ƃ߂̏ꏊ�ł��B
���Ȃ킿���⍜�����u�����u���A�d(���イ����)�v�ł��Ƃ߂�����Ɗ��Ⴂ���������B
�킴�킴���z�c��L�������ړ����Ă��������Ă��܂��B
���C����������Ȃ����Ȃ��̂ł����A
���ɖ߂��Ă����d�œnjo���܂��B
��y�^�@�̎����Q��͎��҂̈������肤�ǑP���{(�����悤)�ł͂���܂���B
����ɔ@���̖{��̖@�����ォ��́A�����肤�K�v�͂���܂���B
��������A�̐l�̕�����������Ă���̂��B�̐l�̎v�����p���A
���o���u�����Ɓv�Ƃ��Đ��M��(���傤����)�₨�o��ǂ݂܂��B
�����͏�ɁA���̂��߂ɐ�l�i�̐l�j�����p�ӂ�������������(�Ԃ���)�ł��B
�y���߂̉̎��z
����13���̃X�|�[�c�̓��͊G�{��Ƃ�Ȃ������������13����ł��B
�挎�A�m�g�j�̒��h���u�A���p���v���I�����܂����B
��Ȃ�����������v�w�̐��U��`�����h���}�ł����B
�푈�Ƃ����ߎS�Ȍo��������������A
�u�{���̐��`�Ƃ͉��Ȃ̂��v�������ӎ������v�w�́A
�����ĂЂ����肩���邱�Ƃ̂Ȃ����́A�u�t�]���Ȃ����`�v��T���܂��B
�����Ă��悻20�N��A
50�Ő��Ɂu�A���p���}���v�ɂ��ǂ���܂��B
�����Ă���l�Ȃ�N�ł���Ђ�����p����͂���q�[���[�ł��B
����Ȓ��h���̍ŏI��ł����B
�A���p���}���a�����炨�悻20�N�B
�A���p���}���̃A�j���������n�܂�܂��B
��т����̊ԁA�ˑR�A������̒�(�̂�)�����@���܂��B
��t�ɂ͓�����ŗ]��3�����Ɛ鍐����Ă��܂����B
�c���ꂽ���Ԃ��Ȃ�����m���l�B
����̃\�t�@�[�ŁA
��Ȃ�����͉�����ɁA�u�����ł��邱�Ƃ͂Ȃ��H�v�Ƃ����˂܂��B
������́u���̈�ԍD���ȉ̂��̂��Ăق����v�ƁB
��Ȃ�����̓A�j�������ɂ������č�����u�A���p���}���̃}�[�`�v���̂��܂����B
�u�������@���ꂵ���@�������낱�с�@
�@�@���Ƃ��@�ނ˂̂������@������ł���v
�Ƃ��낪��(�̂�)����́A
�u���߂�c�c�����������߂ɏ������̎��B���ꂪ�����v
�u�{�c�ɂȂ������H�v
���̓A���p���}���̃}�[�`��
�u�q�ǂ��ނ��̃A�j���̉̎��ɂӂ��킵���Ȃ��v��
�ꕔ�蒼�����ꂽ�ӏ�������܂����B
�{���͍ł��������������ӏ��ł��B
�������c�c�A�v�����Ă�Ȃ�����͂������Ȑ��ʼn̂��܂����B
�u�������@���ꂵ���@�������낱��
�c�c���Ƃ��@�w���̂����I���Ƃ��Ă��x�c�c�v
�����I����āA
���炭�̒��ق̌�A
������͌����܂����B
�u�c�c���肪�Ƃ��B�����A���悤���������B
�����������̉̂ɍ��߂��v���B
���͂����I���B
�ł�����́A���ׂĂ̏I����̂��āA�p����Ă����B
�A���p���}���̊�݂����ɁB
�₫�A�����邱�Ƃ́A�ނȂ������Ƃ�Ȃ�����B�c�c�v
�y�p���z
�A���p���}���̊�B
����͂�Ȃ��v�w�����U�����Č����o�����g���l������́h�ł��B
�q�ǂ��̂��Ȃ���l�ł����A
���̉��l�ς͕K���p����Ă����B
���̂Ȃ炱�́u�t�]���Ȃ����`�v�͎���������Ēʗp���܂��B
�c�O�ł����������͂��������̏I��肪����Ă��܂��B
���������̌�A�������l�ς̐l�������Ă��Ă����Ȃ�A
�l���̍Ō�͐�]�ł͂Ȃ���]�ł��B
�r��������Ȍ̐l�̉��l�ς��p�����Ԃł��B
���V�͏�y�^�@�łƂ߂܂����B
���̎��́A�̐l�������d�̈���ɔ@���A
���̖{��ł���u�����ĂЂ����肩���鎖�̂Ȃ��^���v
�u�N������Ԃ��Ƃ̂ł�����́v�����������A
������x���ɐl������܂ꂽ�����Ӗ����܂��B
�{��̌����́A
�u�݉䓾���c�c��s����, �s�搳�o�c�c�v�B
����́A
�u���������Ă���Y�̂��Ȃ������������B
�c�c�K���킪��y�ɐ��܂ꂳ�������B���ꂪ�ł��Ȃ���A���Ƃ���J���Ȃ��v�Ƃ������{��ł��B
�����Ă��̖{��̐��A�̑��i�������j���u��و���ɕ��v�ł��B
�����̊�����������A���p���}���Ȃ�ʁA
�����̂�����������u��و���ɕ��v�̖��ɂ��߂đS�Ď��ɐU������Ă����܂��B
���A����ɂ��܂Ƃł����A������x�����Ă���Ƃ����̂���y�^�@�̂����ł��B
��قǂ̒�����̑䎌�ɂ́A�����ꌾ����܂����B
�u�����̂��̎c��̖��A������ɂ����邫�ˁv
�u����������v�Ƃ́A�p����������A���p���}���ɂ��Ȃ������ł��B
�����������āu������������v���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�c��̖���������v�Ƃ́A
�u�c��̐l���A���Ȃ��̂��߂ɐ�����v
�u���Ȃ��ƌ����ė���܂���v
����ȈӖ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
��و���ɕ��ɑS�Ă̌��������߂Ď��Ɏ{���i������j�Ƃ��������܁B
����͌����Ď��Ɨ���Ȃ������Ӗ����܂��B
���̕����܂͎��̂��߂Ɍ��ƂȂ薼�ƂȂ�ꂽ���݂Ȃ̂ł��B
����Ȕ@���̐Ȃ�S�����������A�������(����ق�����)�̂��O�����������܂��B
��ɂ̌����ɏƂ炳�ꑱ����l���̘H�ł��B
�ϔY���邪�̂̕s���̏����Ȃ��ŘH(��݂�)�ł����A
����̔ӂ̂��Ƃ��A��������Ƃ������ǂ�̍s�H(������)�ł��B
�u�������сv������������̂�A���ꂪ�O���̓��ł��B
�u��و���ɕ��v���̐l�̉����̊肢�Ƃ��܂��B
�u���Ƃ����̂����I���Ă����̐S�z������܂���B
����قǂ̑傫�Ȓl�ł�������̂ɂł������l���ł����B
�������ĂЂ����肩���邱�Ƃ̂Ȃ��^���B���Ȃ炸�p����Ă����܂��v�Ɗ肤�̐l�B
�̂Ɏ������͎p���̂ł��B�@
�y���܂��F��{���̐S�z
����������̈�e�ɂ͎�����킹�₷���ł����A
�����Ȃ����̕��d�ւ͎�����킹�ɂ����ł��傤�B
�܂��Ă₨�O���𐺂ɏo�����͗E�C������܂��B
�ł��A�ŏ��̊�{���̐S�ł��B
�s���Ƃ��Ȃ���������܂��A
�m���ƈꏏ�ɂ����d�ł���A�����Ă��O�����܂��傤�B
���̂�������Ă��܂��B
�X�|�[�c�̊�{�Ɠ����ł��B
�o�X�P�b�g�{�[���̃V���[�g�̃|�[�Y�A
�o�g�~���g���̃��P�b�g�̎������A
�ŏ��͋����ł��B
�����������Ƃ��̕������R�ł���A
�������邱�Ƃŋ������A
��y�^�@�Ƃ������l�ς��g�ɂ��̂ł��B
��1
���ۂ̂�Ȃ�����������̌��t�ɂ����l�̓��e������܂��B
�u���`���Ă����̂́A���ꂪ�t�]�����ł���B
�l�炪�����ɂȂ��Č������֑���ꂽ���A����͐��`�̐킢�ŁA�����̖��O���~��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��ƌ���ꂽ��ł��B
�Ƃ��낪�푈���I����Ă݂�A�����������Ɉ����z�ŁA�N�������Ă������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��傤�B
�i�����j
�悤����ɁA�푈�ɂ͐^�̐��`�Ƃ������̂͂Ȃ���ł��B
�������t�]����B����Ȃ�t�]���Ȃ����`���Ă����̂́A�������������H
�i��Ȃ��������w���̂��߂ɐ��܂�Ă����́H�x�o�g�o���ɁA2024�N�j
���p���R�`��
�i�����j ���`����
�����̖ړI
�y�����̐S���z
�x����̉Ƃ̂����d�̏�ɂ͂���Ȍ��t���z�ɓ����Ă��܂��B
�����̐S���@�l���͎R�⑽�����̓�
�җ�@�Z�\�˂ł��}���̗������́@��������Ɖ]��
�ËH�@���\�˂ł��}���̗������́@�܂��܂������Ɖ]��
����@���\���˂ł��}���̗������́@�����ȘV�y�@���ꂩ���Ɖ]��
�P���@���\�˂ł��}���̗������́@�Ȃ�̂܂��܂����ɗ��Ɖ]��
�Ď��@���\���˂ł��}���̗������́@�����������Ă�H�ׂĂ���Ɖ]��
�����@��\�˂ł��}���̗������́@�����}�����Ƃ��悢�Ɖ]��
�����@��\��˂ł��}���̗������́@�������Ă����炩��{�c�{�c�s���Ɖ]��
�C�ɂȂ�̂��u���}���v�ł��B
���������N�����}���ɂ���̂��H
�f�C�T�[�r�X�i�ʏ����j�̑��}�T�[�r�X�ł͂Ȃ������ł��B
�c�c���_�H
�y�c���̗[���z
���ĂX���P�T���͌h�V�̓��ł��B
�u���C�Œ��������Ă��������B�v
�c�t���̎q�ǂ������Ɏ莆�������ă|�X�g�ɓ������Ă��܂����B
�����Ƃ������N������������c���Ƃ���Ȏv���o������܂��B
�����̑c����90�߂��Ă��āA���肩��́A
�u�V�@���܁i�c���j�́A�X�O�߂��Ă��傫�Ȑ��ł����C�ł��ˁB�����܂����B�v
�������m���Ɏ���Ă���c���ł����B
�Ԃłǂ����֍s�����Ƃ������Ă��u�ǂ��ɂ��s�������Ȃ��v�B
�H�ׂ������̂������Ă��܂����B
�悭�Q�Ă��܂����B
�Ⴂ���͎v���Ă��܂����B
�u�N���Ƃ��ĉ����ǂ����Ƃ�����̂��B�v
����Ȃ�����̗[���B
�Ƒ��ł��[���i�[���̂����d�ł̂��Ƃ߁j�̎��ł����B
�����Łw�d����i���イ�������j�x��njo���āA�݂ȑ䏊�ցB
�Ō�Ɏ��������d�̔���߂悤�Ƃ���ƁA�܂����Ƃ߂̐������܂��B
�U��Ԃ�Ƃ܂��c�������߂����Ă��܂����B
��l�ŒW�X�Ƃ��o���ƂȂ��Ă��܂����B
���܂��ĕ����Ă��܂����B
�c���̂��߂��I���A�u�i�}���_�u�@�i�}���_�u�v�A�c���̔O�����������Ă��܂����B
���̎��v�����̂́A
�u���̑c���̂��O���́A���̂��邨�O���Ɣ�ׂđ��������[���̂ł͂Ȃ����B�v
���͂̂��O���ł��B
���g�݂͂ȓ������K���~���Ƃ�������ɂ��܂̂��ׂĂ̂������܂����u��و���ɕ��v�ł��B
�������X�O�������A�F���قƂ�ǖS���Ȃ�A�g�̂������Ȃ��Ȃ�A�ǂ��ɂ��s���Ȃ��c���B
�u����Ȏ��Ƃ��Ă�������A���Ă�������A����ł�������B�v
�Ⴂ���ɔ�ׁA����ɂ��܂̂����̖��킢�̐[���͌v��m��܂���B
�u���߂��ނقǖ��킢���[�����̂�����Ȃ�A���������Ă��ǂ������B�v
�����v�����̂ł����B
�y�������̗��R�z
���Ď���ɕ����ĉ������������܂����B
�u�Ȃ��������������̂ł����H�v
�u����Ⴀ�A�N�����Ƃ肩������ƁB�v
�u�����U�����܂��B�G�߂̂��肩��肪�y�����ł��B�v
�Ȃ��ɂ́A
�u�����V���ǂނƁA�����Ȏ��������邶��Ȃ��ł����B�ʔ����āB���������Ȃ��ƁB�v
�u�����ł��ˁc�c�B�Ƃ���ň����͉�������܂��������H�v
�u�c�c�Y��܂����B�v
�݂Ȃ��ꂼ��A�����ȗ��R������Ǝv���܂��B
�����̒��]�J�����_�[�ɂ͂�������܂��B
�u�������܂�����̂��@���@�����̂��Ñ��v
�����Ă������Ă��܂����������A
���߂��ނقǖ��킢�[�����@�ł��B
�Z�\�����Ďd������i���ƂȂ�A
�������������A
�u�����������A����ǂ��Ȃ�́H�v
����Ȗ₢�����������ɁA
���@�ɂł����Ă݂܂��H
�u�����������A�Ȃ�Łw��و���ɕ��x���Ă����́H�v
�����ȗ��R�����낤�Ǝv���܂��B
�S�����������A�����܂ɏW���ł���Ƃ����̂����邩������܂���B
�c�c�ق��Ă����炱�̐S�A�����v���������������̂ł͂���܂���B
�������{���́u��و���ɕ��͖��ƂȂ萺�ƂȂ��������܁v�Ƃ������킢�ł��B
���O���́A
���̖����̂��A���̋��������ł��B
���ɐ_�̂悤�Ɏ��ʒ��O�ɂ���Ă���̂�����ɂ��܂ł͂���܂���B
���ł��ǂ��ł��Q�镧�A
�����ė��������Ȃ��Ɗ��ꂽ�����܂ł��B
�u�허�}�v�i���傤�炢�����j�Ƃ������܂�
�u���}���v�͍��ł��B
�������̔錍�͂킩��܂��A
������h�����N������Ō��C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��A
���������ėǂ������Ǝv���閡�킢����و���ɕ��Ȃ̂ł��B
�����̂��O���̐S��
�Z�\�˂Ŕ@���̋��������́A�u�������~���̂ǐ^�ł����B�v�Ƃ��O���B
���\�˂Ŕ@���̋��������́A�u�܂��܂����킢�[�������߂̖��v�Ƃ��O���B
���\���˂Ŕ@���̋��������́A�u����ł��B�V�y�́@�@���Ƌ��ɓ�l�A��v�Ƃ��O���B
���\�˂Ŕ@���̋��������́A�u�P���ł��B�����������߂ɂт���G��ł��v�Ƃ��O���B
���\���˂Ŕ@���̋��������́A�u�Ď��ł��B�ꗱ�̂��Ăɂ��@���̂����߂�����܂����v�Ƃ��O���B
��\�˂Ŕ@���̋��������́A�u�����ł��B�e�a���l�������̍܂Ő�������܂����B�������Ԃ̘b�ɗp���Ȃ��v�Ƃ��O���B
��\��˂Ŕ@���̋��������́A�u�����ł��B�������߉ޖ�ɂɓ�����Ă̔����Ɉ���ł��v�Ƃ��O���B
���݂��������������܂��傤�I
�i�����j ���`����
��C���킹
�y��ԑ傫���̂́z
�g����̖@���ł͂�����������͂Ȃ��Ȃ��������Ă���܂��B
�u15��74��91�B��ԑ傫�Ȃ̂͂ǂꂾ�H�v
�u91�H�v
�u������74�I�v
���̂��B
���͑S�ĉʕ��ł����B
15�́u�C�`�S�v�A74�́u�i�V�v�A91�́u�L���[�C�v�B
��������ƈ�ԑ傫���̂͗��ɂȂ�܂��B
�����̌�C���킹���g�����Ȃ��Ȃ��ł����B
�y9��4���z
�u����9��4���̓N���b�V�b�N�̓��ł��B�v
����Șb���܂����B
�u�N�i9�j���V�i4�j�b�N�v�Ɠǂތ�C���킹�ł��B
�ʔ����̂ő����q�ǂ������ɁB
�u�����͉��̓����m���Ă�H�v
�u�N�V�i94�j�̓��H�v
�u�N�W�i94�j�̓��H�v
�u����A�N���b�V�b�N�̓��B�v
�u�ւ��`�B�v
���q�ɏ���čȂɂ������܂����B
�u�����͉��̓����m���Ă�H�v
�u�c�c�m��Ȃ��B�v
�Ȃ͏������Ă��܂����B
���܂킸�A
�u�N���b�V�b�N�̓��Ȃ��āB�v
�u�c�c�N���b�V�b�N�̓��H
�����͈������ς������́B
����ȗI���ɉ��y�Ȃ�Ē����Ă��Ȃ���B
�����́u�ꂵ�݁i���i9�j�邵�i4�j�݁v�̓���B�v
���������ʂ�ŁB
�y�����̓��z
��C���킹�͍D���ł��B
�����l�ɂ���Ă͂��̂��߂ɁA
�����́u9�v��u4�v�������l�����܂��B
9�́u��v�ɁA4�́u���v��A�z����悤�ł��B
�i�[�����̔ԍ��u���|�X�v�́A�{�l�����Ă̗��݂Łu���|�P�v�ɁB�j
9��4�����ꂵ�݂̓��������Ȃł����A
�����������ł́u��؊F��v�Ƃ����āA
�ꐶ�U���ꂵ�݂̓��ł��B
���N���āA�W���M���O�����Ȃ���u�f���炵�����Ă����B�����͗ǂ������v�Ɗ������Ȃ���A
���̔����Ԍ�ɁA�v�w�Ō��_���A�u�Ȃ�Č��ȓ����v�Ƃ����̂͂悭����܂��B
�ꂵ�݂Ƃ͂����w�����킹�̖����ł��B
����Ȏ��ɐ����ꂽ���߉ނ��܂̋������A
����ɔ@���̕���B
�{������āA��y�����Ă��Ƃ����b�A
���̕�������e�a���l�́u�ێ�s�́v�Ǝ�����܂����B
�u�҂��Ă��Ă͋~���Ȃ����҂�����v�i�쑽���K���A�h���}�wTOKYO MER�`����ً}�~�����`�x���j
�u����y�ɕK�����܂ꂳ����v�Ƃ����肢�́A
�u�ۂߎ���Ď̂ĂȂ��v�Ƃ����M�O�̕\���ł��B
���̊肢�̊����`���u��و���ɕ��v�̖����ł��B
�u��و���ɕ��v�͒P�Ȃ閼�O�ł͂Ȃ��A
��y�̐^���������Ƃ�̂���y�^�@�Ƃ��������ł��B
�u����9��4���́w�ꂵ�݁i��[9]�邵[4]�݁j�̓��x�������B��ς������B�v
�u����9��5���́w��s��s�i��[9]���傤[5]�j�̓��x�������B���������B�v
�u����9��6�����w��J�i��[9]��[6]���j�̓��x�������B����ǂ������B�v
�u����9��7���́w���i��[9]��[7]��j�̓��x�������B�h�������B�v
�u����9��8���́w����ށi��[9]��[8]�݁j�̓��x�������B���s���肾�����B�v
�c�������������A��s�����ڂ�₷�������ł��B
��������و���ɕ��̂��O����ʂ��āA
�u�����炱���@�����܂͗���Ă����Ȃ������Ɓv�����������A
�ʂ̌�C���킹�������Ă��܂��B
�u��ς��������A����9��4�����w��(9)���̐��i4�j�݂��ޓ��x�������B�ܑ̂Ȃ������B�v
�u�����������A����9��5�����w��(9)�Ɓi5�j�̓��x�������B���O�������ɂł����B�v
�u����ǂ��������A����9��6�����w��(9)����t�̘Z�i6�j���̓��x�������B���肪���������B�v
�u�h���������A����9��7�����w��(9)�����킪�g�ɗ��i7�j�����x�������B���������B�v
�u���s���肾�������A����9��8�����w��(9)�{�i8�j�̓��x�A���O�������āA�h���S�������Ĕ@���ɂ���d�A������ӂ��ł����B�����������B�v
�y�N���b�V�b�N�Ƃ́z
�u��y�o�T�Ȃ�ČÓT�A�Â������B�����Ă�������Ȃ��B�v
�ł͌ÓT����������ł��傤���H
�Â������ł��傤���H
�N���b�V�b�N���y�͂ǂ��ł��傤�H
�N���b�V�b�N�Ƃ́u�ÓT�I�ȁv�Ƃ����Ӗ��ł��B
����z�����̂��u�ÓT�v�ł��B
����ɌÂ���������܂���B
���o�����l�ł��B
�����������C���[�W������A
����͂����������t�ɂ����܂��ł����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�����u�H�킸�����v�Ƃ����l������悤�ɁA
���Ȑl�����܂��B
���w5�N�ɂ��Ȃ��āA�g�E�����R�V�����Ȃ킪���B
�ł������e�͉��Ƃ��H�ׂ����悤�Ɨ�܂��܂��B
�u����������I�v�ƌ����āA�u����ł��v�ƌ��Ɏ����Ă����܂��B
���Ԃ��Ԍ��ɂ��閺�B
�������̔��������ɋC�Â����Ƃł��傤�B
����y�̘b�͒N�����ŏ��́u�H�킸�����v�ł��B
���V�Ƃ��������ʘb�ƒ������ċꂢ�ł����A
�܂��s���Ƃ��Ȃ��̂Ŗ��������Ȃ̂ł��B
���������̔���������m���Ă���l����̂����ŁA
���̊Ԃɂ��u���肪�����v�Ƃ���������悤�ɂȂ�̂ł��B
�i�����j ���`����
�O���̊�
�y�́z
11�N�O�̒��h���w�}�b�T���x��
�j�b�J�E�C�X�L�[�̑n�Ǝ҂ł���|�ߐ��F�Ƃ��̍ȃ��^�����f���ɂ����h���}�B
���{�ɃE�C�X�L�[�u�[���������N�����܂����B
��l���̋T�R���t�i�ʎR�S��j�͓��{�Ɂu�{���̃E�C�X�L�[���v�Ɩz�����܂��B
��ꂩ��߂������m�ȂǁA�n�������Ō����ɐ�������{�ɁA
�N�������߂�����Ă��܂��u�E�C�X�L�[�i���̐��j�v�ݏo�����ƕK���ł��B
��������T�Ԍo�߂��Ă��A���z�̃E�C�X�L�[���ł��܂���B
�����Ŏ�̕��ɑ��k���܂��B
���e�̏����́u�̂����߁v�ł����B
�����F��������S��������ɂȂ�Ƃ����悤�ƍl�����A
��_�Ƀ|�C���g�����߂�ƁB
���u�킵�̏ꍇ�́A�Ă�������B
�킵�́A���`���ƍ��i�������j�ɂ�������Ƃ�����B
�_�����ɍ����������߂āA���������삯�������Ƃ����B
���Ⴏ�ǁA���܂ł����Ă��[���̂������܂����͂ł���B
�Ƃ��낪������A���ꂿ������Ƃ͈Ⴄ�Ă𒍕����Ă̂��B
�c�c���̕Ă�H���Ȃ���A�ӂƎv������B
�����Ƃ͕ʂ̕Ă��g���������͂Ȃ����B
�ق��ŁA���g���Ƃ�Ăɂł����āA���̕Ă��̂ɐ�������B
���̕Ă̗ǂ����ő���ɐ������鍍�͂ǂꂶ�Ⴂ���āB
���炽�߂č���T���n�߂���B�v
���t�͂����ɐE��ɖ߂�܂��B
���܂Łu�������ǂ�ȃA���R�[���Ŋ���������v�ƍl���A
�̂����߂Ă��܂���ł����B
�E�C�X�L�[�̊́A����͌����ł��B
�����́A��͂�l�X�Ȍ����i�V���O�������g�����A�O���[�������j���u�����h���Ă���܂��B
���̒��S�ƂȂ錴�����u�L�[�����g�v�B
�A���R�[���Ŋ����Ă��A�G�b�Z���X�����Ȃ��Ă��A
�X���[�L�[�t���[�o�[�������Ă���Ⴂ�����A
�L�[�����g��T���n�߂܂��B
�����Ă��Ƀ}�b�T���̗��z�̃E�C�X�L�[����������̂ł����B
�y�A���z
�{��̖����͐���̋ƂȂ�B
�e�a���l�́u��و���ɕ��v�̂��O����ɐ������l�ł����B
�N�����s���邱�Ƃ��ł��邱�̘Z���ł����A
����͍��x�ȍs���ł��Ȃ��l�̂��߂̈��Ղȍs�A
���肻�߂̍s�A�����̍s�A�U���̍s�A
�����ł͂Ȃ������������߁A
�e�a���l�́w���s�M�x�����M���܂��B
�����Ăނ���O�������A
�������ϔY��̖}�v���{���̍s�ɂł�����^���̍s�ł���A
���߉ޗl�����ɂ����ꂽ�ړI�ł��鎖�𖾂炩�ɂ���܂��B
���̎����������߂ɁA
����ɕ��̖{���O��I�ɉ𖾂���܂����B
�����Ă��̖{��̒��ɁA
�ϔY�}�v�����ʂ铹�����������Ă��鎖�𖾂炩�ɂ���܂����B
�ł͉�����و���ɕ���^���̍s�Ƃ���̂��B
���l�i�e�a�j�ꗬ�̌䊩���̂����ނ��́A�M�S�������Ė{�Ƃ�����ӁB�i�@�@��l�j
�̂Ƃ����̂��u�M�S�v�ł����B
��و���ɕ��́u�얳�v�̕����ł��B
�����Ɏ��͂�������₷���̂ł��B
�u�M����Ώ�����̂ł��ˁB�v
�u�ǂ����Ε���M���邱�Ƃ��ł���̂��B�v
������u�얳�v�̌��͋A���Ȃ�B
�u�A�v�̌��́c�c
�����������āu�A���v�͖{�菵���̒����Ȃ�B
�u�������v�Ƃ��ӂ́A
�@�����łɔ��肵�ďO���̍s����{�����܂ӂ̐S�Ȃ�B
�u�������s�v�Ƃ��ӂ́A
���Ȃ͂��I��{�肱��Ȃ�B
�u��و���ɕ��v�Ƃ́A�����ʂ�u�@����M����v���ł����A
����́u�@��������鎄�̍s�ׁv�ł͂Ȃ��A�^���́A
�@�����u���ɂ܂�����v�Ƃ������ѐ��ł���A
�@�������������͂��炫�ł���A
���߂�Δ@���̂��{�肪���̂܂܌`�ƂȂ������̂Ȃ̂ł��B
�u��و���ɕ��v�Ƃ���������ʂ��āA
�@���̋����A�@���̎v���i�{��j��s�ׁi��߁j������ł��B
�O��I�ɐM�́u���M�v�Ȃ̂ł��B
��و���ɕ��́u�얳�v�i�A���j���A
���͂ł͂Ȃ����͂̐M�S�ƂȂ鎞�A
���̓�و���ɕ��͐^���̍s�ƂȂ�̂ł��B
�y���M�z
���|�]�_�Ƃ̋T�䏟��Y����́w�e�a�x�`���Ŏ��̂悤�ɐe�a���l��]���Ă��܂��B
�e�a�̐M�S�́A�F����Ƃ��땷�M�̈��ɂ���悤�ł���B
�g�u�����v�Ƃ��ӂ͖̂{��������āA�^�ӐS�Ȃ��Ƃ��ӂȂ�A
�܂��u�����v�Ƃ��ӂ͐M�S������͂���@�i�݂̂�j�Ȃ�h�ƁA
�w��O���O�ؕ��x�ɂ��q�ׂĂ��邪�A
����͔ނ̑S���͂ƌ����̍��q�ɗ����ԓx�ł���B
�u��i���j�v�M�S���l����Ƃ��ӕ\���͋����i�����j�ɂ����Ȃ��B
���͏C���ɔ���������ϑz�ƕ��ʂ́A
�e�a�̐��U�ɂ킽���Č��������߂��Ƃ���ł���B
���@�ł͂Ȃ����@�\�\���ꂪ�e�a�̍��{�ԓx�ł������B
�����āu���܂͂肽��M�S�v�\�\���ꂪ�ނ̑S�����ł������B
���܂�肽����̂Ȃ邪�䂦�ɁA
�����ɂ͂����Ȃ�Œ艻���ƒf����邳��Ȃ��B
�������S�ɕ����A���S�ɐM�y�i���傤�j����̂݁B
���̔ϔY���S������]�n�̂Ȃ��u��و���ɕ��v�̑��݂�m��A
�����`�������������e�a���l�B
�u����ɂ��܁A���������������v�Ə̂���̂ł͂Ȃ��A
�u����ɂ��܂�����ł�������v�ƕ������O���B
�O����i�̂���j�l���ǂꂾ���S���W���ł��邩�A
�O����i�̂���j�l���ǂꂾ���߂Ȃ��Ă��邩�A
�O����l�̐S�̐��炩����_�́A�m���c�c�A
���̂悤�ȁu���́v�̏��ɁA
�O���̖{���̖��͂���܂���B
��������ʂ��āA
���͉���̐M�S��������������ł��B
�N���������ł�������Ŗ{���̃E�C�X�L�[�i���̐��j�����߁A
�̂ƂȂ�L�[�����g���݂����}�b�T���B
�N�������y�ł���Ղ����^���̍s�Ɓi���@�̖��j�����߁A
�̂ƂȂ�M�S���������������e�a���l�ł����B
�i�����j ���`����
������
�����̘Z������\�ܓ�
��������햃�i�Ђ܁j�̐Ԃ��炭��i�؏��q�j
�y������z
����Ȕo����������ł��傤���B
������Z������\�ܓ�
�����Z���͍L���Ɍ��������������A
����͒���Ɍ��������������A
�����ď\�ܓ��́A�I��̓��ł��B
�O�̓���Â��Ɍ�邾���ł����A
�u�푈��Y���ȁ@���̎S�����������ȁv�Ƃ���������������悤�ł��B
�u�m��܂���B�v
�u�ǂ������Ӗ����킩��܂���B�v
�Ⴂ�l�̑���������ȕԓ��ł����B
�S���Ȃ����A�{���Ƀs���Ƃ��Ȃ��̂��B
�`�h�ŗǂ����璲�ׂĂق������̂ł��B
�����āA���炽�߂Đ푈�̔ߌ��A
���S�i�߂�Ƃ��Ȃ���S�ɒp���Ȃ����Ɓj�ȏɂȂ鎖�̋��낵����
�Y��Ȃ��悤�ɂ��������̂ł��B
�y�����͐l���I�Ȃ��z
8�N�O�i2017�N�j�̕���29�N10���A
�X�d���i���� ���������j����̍u�����܂����B
2016�N�A���E�̃A�����J�哝�̂����߂Ĕ픚�n�E�L����K�₵�܂����B
���̎��A�I�o�}�哝�̂��n�O�������肪�X�d������B
���E�I�Ȓ��ڂ��W�߂܂���
�X�d�������8�̎��A�L���Ŕ픚���܂��B
�u���ł͂��̎��̋��낵�������b���������܂����B
�Ƃ��낪��l�ɂȂ���������A�L���ɃA�����J���̕ߗ�����������m��܂��B
���̕ߗ���������ɂǂ��Ȃ����̂��A�N���m��܂���B
�u���̌��������������ł��̔N�ɖS���Ȃ����l�͖�14���l�B
���{�l�ł�������Ȃ��]���҂�����̂Ɂc�c�B�v
�u�A�����J�l�̎��̓A�����J�ł���Ă��炤�����c�c�B�v
�X�����40�N�ȏォ���Ē��������A
�픚������12�l�̃A�����J���̖��O����肵�A
�⑰���݂��Ă͘A�����܂����B
�u�Ȃ��č����m�̏��������悤�Ǝv�����̂ł����H�v
���ĐX����͔��S�n�ɋ߂����w�Z�i�L���s�����j�ɒʂ��Ă��܂����B
�A�����J�ߗ������e����Ă����ꏊ�����������B
�u�����͂��܂��܂��̊w�Z���痣�ꂽ���ɂ����̂ŁA�����̒������������B
���̊w�Z�̗F�l�͊F�Ȃ��Ȃ����B
�P�Ȃ�G���̐l�ԂƂ͎v���Ȃ������B�v
�܂����W�I�ŃA�����J�l�̈⑰���u�i���������́j�p�C���b�g�̏�����m��Ȃ����H�v�Ƃ����˂�����������������ł��B
�������̂̓}�b�J�[�T�[�����������Ƃ��B
�푈�̈⑰�̔߂��݂͓G���������B
�Ȃ�Β��ׂĂ݂悤�Ǝv�����̂������ł��B
2���Ԃ̍u���B
�����̋��낵���A�܂��l��������Ĕ߂��݂ގ��������Ă��炢�܂����i��1�j�B
�y�W�܂�z
�u�i�푈�́j�������n�܂�����A�~�܂�Ȃ��v
�i���i�q�^�Ђ߂�蕽�a�F�O�����ف@�ْ��j
�푈���N�����Ȃ����@�B
���̈�́A���肩�����푈�ɂ��čl�����A��荇����������Ƃł��B
��l�ō����̃j���[�X���ςĂ���ƁA
�܂��푈�e�F�̋C�������萶����\��������܂��B
���Ƃ��A���R�[���ˑ��ǂŋꂵ�ސl�B
��������߂���@�ɂ́A��Â⎡�ÁA
���܂Ȃ��������𐮂���Ȃǂ�����܂����A
�u�f����v��u�`�`�i�A���R�z�[���N�X�E�A�m�j�}�X�j�v�Ƃ�����
�����o�������l�����Əo��ꏊ���ƂĂ��L���ƌ����܂��B
�o����Ă����ɉ����ǂ��Ƃ����킯�ł�����܂���B
���݂��ɂ����ŋꂵ�����̎���b�������ł��B
��������\����A�������������A����������������܂���B
�܂�Ȃ���������܂���B
����ǂ����ꂪ���~�߂ɂȂ邻���ł��B
���������Ă��܂������Ȃ邨���B
�u�ǂ����Ă���������ł��܂��B�v
�u��͂���͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�v
���������݂��ɁA
�u�ł�����������łǂ�Ȏ��s���H�v
�u�c�c��Ȑl��߂��܂��܂����B�v
�푈�����A���݂����W�܂�A
�b�������A�b������Ȃ��Ă����������ł��A
�傫�ȃA�v���[�`���Ǝv���܂��B
�y�@��z
�u����⌤�C��B
�푈���A���ʖ��ɂ��ėL���ł��B
�������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��͖̂@�b��B
�����̖��A
���̐l�ԋ�̖��ɂ��ėL���ł��B
���ꏏ�ɖ@���܂��傤�B
��1�F
�����C��̍Ō�A�f���g���̈��A�Łu�������i���݂傤���傤�j�v�̘b���o�܂����B
�������͈�̐g�̂�2�̓��������ł��B
���ɓ������������B
�w�G�o�x�ɂ͎��̂悤�Ȃ��߉ނ��܂̂��b������܂��B
���A���ɏ�ɍ݂����A���X�̔�u�A���ɔ����Č����A
�u�����A��k�B���A����@���̒�Ȃ�B������ɕ������Q����Ɨ~����B�v
�������A
�u���������ɂ��炸�B�̐�R���ɒ�����Ė����ċ����Ƃ��B��g�Ȃ�B
�ꓪ�͏�ɔ��Ȃ�ق�H���A�g�Ɉ������߂�Ɨ~���B
�ꓪ�͂��Ȃ킿���i�̐S���Ă��̌����삷�ɁA
�w�ނ͏�ɂ����D���̉ق�H����B�䂩�ē�����x�ƁB
���Ȃ킿�ł̉ق����Ă����H���A�͋�Ɏ������߂�B
�m���Ɨ~���B
���̎��Éق�H���́A��g����Ȃ�B
���̎��ʼnق�H���́A��k�B������Ȃ�B
�̎��ɉ�Ƌ��Ɉ�g����B
�Ȃ����S���A���䂪��ƂȂ邱�Ƃ܂������̂��Ƃ��B
�i�w�G�o�x���O�iT0203_.04.0464a�j

���̋������́A
����y�̒��Ƃ��āw����Ɍo�x�ɐ�����܂��B
�����āu������E���Ύ���������ł��܂��v�������ɁA
�푈�̋������A���a�̑���������܂��B
�i�����j ���`����
���ꂸ�E��������
�y��͂ǂ����Đ��́H�z
��͂ǂ����Đ��́H�@�@�C�̐F�����邩���
�a�c������쎌�u�ǂ������v�̖`���ł��B
�q���̉��C�Ȃ�����ɂ₳����������ƂĂ��f�G�ȉ̂ł��i���샌�~����̉̐����������j�B
�c�t���ł��q�ǂ��ɂ͂悭���₳��܂��B
�u����ȁ[�ɁH�v
�u����̓X�s�[�J�[�B�l�̐���傫�����ē͂��Ă�����B�v
�u����ȁ[�ɁH�v
�u����͉����搶�̑厖�Ȗ{�i�~�[�e�B���O�m�[�g�j�B�v
�y���̔g���z
�c�c���ꂩ��\���N�B
���Z���̎��Ƃł��B
�uWhy is the sky blue?�i��͂ǂ����Đ��̂ł����H�v
�uBecause the color of the sea reflects�v
�Ɠ�����搶�͂��܂���B
�u����͌��̋��܂������ł��B�v
���Ƃ�����ȓ������Ԃ��Ă��܂��B
�ǂ��������Ƃ��B
�܂����z�̌��ɂ��ė�������K�v������܂��B
���z�̌���1�̌��̂悤�ŁA
���͂����Ȕg���̌��������荇���Ăł��Ă���̂������ł��B
�ł��g���̒����̂͐ԐF�ł��B
�����Ĕg�����Z���Ȃ�ɂ�āA
��A���F�A�A�A���F�ƂȂ�A
�Ō�͎��F�ł��B
���̔g���̓v���Y���Ƃ������̂��g���Ď�������ƕ�����܂��B
�v���Y���Ƀ��C�g�Ă�ƁA
���C�g�̌������܂��܂��B
�g���̒����ɂ���Đ܂�Ȃ���p�x���قȂ�A
���ʁA���̂悤�ȐF��������̂ł��B
�v����ɑ��z�̌��̒��ɂ͂����ȐF�̌�������A
�F�ɂ���ċȂ�������قȂ�̂ł��B
�ł́u�ǂ����ċ�͐��̂ł��傤�H�v
�n���ɂ͋�C�̑w������܂��B
���z�̌����n���ɂ������A
���̋�C�̑w�̎_�f�⒂�f�̕��q�ɓ�����̂ł��B
���ꂼ��̔g���̌��͂��ꂼ��ɋȂ���A
�U����Ă����܂��B
���̍ہA�g���̒Z���F�̌��͋ŋ����Ȃ���A�[��ƎU���܂��B
���F�A�������l�ł��B
�i�t�ɔg���̒������͎̂U��炸�A���̂܂ܒʉ߂���̂������ł��j
�F�̌�����ŎU�����邱�ƂŁA��͐��̂ł��B
�c�c�킩�����悤�Ȃ킩��Ȃ��悤�ȁB
�i�ڂ��������������ǂ����j
�y�l��o�V�z
�u�Ȃ�������ȂɊD�F�Ɍ�����̂��H�v
���߉ނ��܂͂��đ傫�ȋ^��������܂����B
�L���ȃG�s�\�[�h�u�l��o�V�v�ł��B
���̖傩��U���ɂł�ƘV�l�ɁA
��̖傩��U���ɂł�ƕa�l�ɁA
���̖傩��U���ɂł�Ǝ��l�ɁB
�ǂ�������ē���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꂵ�݂ƕ����V���b�N���܂��B
�u�ǂ����Ă���ȋꂵ�݂��Ȃ�������Ȃ��̂��H�v
�Ō�A�k�̖���ł�Əo�Ǝ҂ɂ����܂��B
�^�������߂鐶�����Ɋ������A
�Q�X�̎��A�ꂵ�݂������������铹�A��E�̓���T���ɏ�𗣂��̂ł��B
�R�T�Ńu�b�_�A�^����̓����A
��S�T�N�̊ԁA���̌�����^������@����܂����B
���̐l�̗����ɂ��킹�Ă₳�����[��������܂����B
���߉ނ��܂����ςɓ�������A
�c���ꂽ��q�����̋������܂Ƃ߂܂��B
���o�̓o��ł��B
�y�O�@�痣��Ȃ��z
�ǂ̂��o����Ȃ��߉ނ��܂̂����ł����A
���ʂ���͎̂O�ł��B
���s����i���催�傤�ނ��傤�j
���@����i����ق��ނ��j
���ώ�Ái�˂͂Ⴍ���傤�j
�O�@��i����ڂ�����j�Ƃ����܂��B
�Ƃǂ܂邱�ƂȂ����肩��錻��������܂��B
�����̂ɂ��Ƃ����K�v�̂Ȃ��^��������܂��B
����ǂ��Ƃ���Y�ގ������B
���̋�Y����������炩�ȋ��n�A�^�@�̐��E������܂��B
�O�@�痣��Ȃ��̂������̑匴���ł��B
�y��y�^�@�z
���ꂩ��P�O�O�O�N���܂�o�߂��A
�e�a���l�͏�y�^�@���Ђ炩��܂����B
�{��͂ɂ��Ђʂ��
�ނȂ���������ЂƂ��Ȃ�
�����̕�C�i�ق������j�݂��݂���
�ϔY�̑����i���傭�����j�ւ��ĂȂ�
�{��͂Ƃ́A���̊肢�ł͂Ȃ����̊肢�ł��B
�����肢�����ȏ�ɁA
���̕�������Ȋ肢�A
�����Ă��̊肢�𐬏A����͂����Ȃ��A
���̗͂��ӂ�ނ���͂��炫�u����v�A
��������Ă����鐢�E�𖾂�����܂����B
���͂̐��E�ł��B
���ƌ����ė���Ȃ��ƌĂԐ��̌��ł��B
�y���̌��z
�v���Y���ɂ��Ă�ƌ��͂��悻���̐F�ɂ݂��܂��B
�@���̖{��������悻���̐F���݂��܂��B
�݉䓾��
�P�@�\���O��
�Q�@���S
�R�@�M�y
�S�@�~���䍑
�T�@�T���\�O
�U�@��s���ҕs�搳�o
�V�@�B���܋t��掐��@#eb6ea5
���ꂼ���Ȕ@���Ƃ����^���̐F������킵�Ă��܂��B
���̐F���������̂����@���ł��B
���~�̎����A�ǂ̂������З��~��Ƃ����@�����J����܂��B
��y�^�@�́u�����i�����j�v�Ƃ�і@��������܂��B
�u���ꏏ�ɖ{��̂��S���܂��傤�B�v
�S���̏Z�E����́A�F����̗�����S�҂��ɂ��Ă��܂��B
�y����Ȃ����@�z
�u�{�肩�痣���ȁv�Ǝ����ꂽ�e�a���l�B
�ł͂ǂ�����Ζ{�肩�痣��Ȃ��̂��B
���O�������܂��B
��و���ɕ��̂��O���B
���ł��ǂ��ł��̂��邱�Ƃ��ł��܂����A
���̂�����͖{��ɂ���܂��B
�ł͂ǂ�����ΔO�����痣��Ȃ��̂��B
�����d������܂��B
�Z�܂��ɗ�q�������]�V���邨�O���̏�������܂��B
�������A�葫�����A
�����܂̐��E�A�^���̐��E�ɁA�肢��ʂ��Ăӂ�邱�Ƃ��ł��܂��B
�ł͂ǂ�����Ε��d���痣��Ȃ��̂��B
���@���ɎQ��܂��傤�B
������Ƃ��ɔ����̂����Q��B
�����ł��������܂��B
���������Ȃ��A���ɖ{��̘b�A����y�̘b�����Ƃł��B
�ł͂ǂ�����Ζ@�����痣��Ȃ����B
�c�c�{���Y��Ȃ����Ƃł��B
�i�����j ���`����
�肢�ɐ�����
�y���[�z
���N�����[�̎����ł��B
�u�ɂ����傤�F�肱�ǂ����v�́A
�قڈꃖ���O���班�����q�ǂ����������[���������Ă��܂����B
�Ȃ�Ȃ��n�T�~��m������K���Ȃ���A
���݂�����A���A�Ђ�������������A�L������A���傤����A
�����킢�����肪�ł��Ă����܂��B
�����čŌ�ɒZ���Ɋ肢���������܂����B
�u�A���p���}���ɂ����܂��悤�Ɂv�i�Ђ܂�j
�u���������肪�ł���悤�ɂȂ�܂��悤�Ɂv�i�݂���j
���N�͐搶�����肢���������܂����B
�u�J�[�v�D���I�v
�u�܂��ɂ������̂����������܂��悤�Ɂv
����A�����̎q�ǂ���Łu�݂�Ȃ̊肢���́H�v�Ƃ����˂Ă݂܂����B
�u�G�����ɂȂ肽���v
�u�i���ɐ����Ă������v
�u���͂��ق����v
�q���炵���Ȃ��肢�i�A�Ă������~�]�j�������Ԃ�Ɣ�ь����܂����B
�����Z���ɏ����܂����B
�u�݂�Ȃ��̂̂��܂������Ɓ@�����ł��Ă���܂��悤�ɁB�v
�y���͂̊肢�z
�l�Ԃ͊肢�������A����Ɍ����ĕ��ސ������ł��B
�肢���Ȃ��̂͂��т������̂ł��B
��y�^�@�̋����̒��S�́u�肢�v�ł��B
�����Ă���́u����ɂ��܂̊肢�v���w���܂��B
�u���͖{��v�Ƃ����܂��B
�������肢�������đO�ɂ�����ł����悤�ɁA
�����܂��肢�������Ă͂��炢�Ă����܂��B
�����܂͉����肢�A
����ɂ��܂͉������ꂽ���B
�u���̋�Y���ǂ����c�c�v�Ɛؖ]���鎄�ł����A
�����d�̑O�ɍ��鎞�A
�u���̋�Y���ǂ��ɂ����āv�Ɗ���邨�S���܂��B
�����Ēm�炳���}�v�̂킪�g�ł��B
���Ɛ^���̐l������ނ킪�g���A
���͐^���ʂ���Ƃ߂Ă����܂��B
���_�A�����肢���߂�K�v���Ȃ���������܂����B
�@���̂����߂̌����A
�u�����i����ǂ��j�v�ň�t�̍��ł����B
�y������z
��ȔV�����@�i����ɂ����ǂ��j
�����{��@�i�т傤�ǂ������������j
�������S�@�i�ǂ��قڂ�������j
�������y���@�i�������傤�����������j
�i���������j
�u��킭�́A����[����ɗl��]�����������āA
�����Ɉ�Ɏ{���A
���������S�i�M�S�̂��Ɓj���āA
���y���ɉ�������B�v
�njo�̍Ō�̎l��A�u������i����������j�v�Ƃ����܂��B
�@�����܂̋~���ɂł����A
�����肤�K�v�̂Ȃ����ł����A
�����炱���A
�u����y�ɐ��܂ꂽ���v
�u�݂Ȃƈꏏ�ɐ��܂ꂽ���v
����Ӗ��A�u�肢�v�������܂��B
�u�ł���ΐ��܂ꂽ���v�Ƃ����W�����҂ł͂���܂���B
�u���Ƃ��Ă����܂ꂳ�������v�Ɗ肢�A
�u�K���������Ă݂���v�ƌ������ӂ�ނ����镧���܁A
���̂��S�E���d���Ԃ�ɂ����������̂ł��B
���̐S�������A�u���܂ꂽ���v�ł��B
�l���̔��������A�u�㐶�̈�厖�v���d�݂𑝂��Ă�������B
���߂̍Ō�ɁA
�@�����܂̉���̂��S����сA
�ꏏ�ɂ���y�ɐ��܂ꂽ���Ɗ肤���Ƃł��B
�i�c�c���A�����͎v���܂��H
�ǂꂾ�������������Ă��Q�肽���Ǝv���Ȃ��H
�悤��������������Ă��������܂����B
���@�����A�ł͂Ȃ��w�V�ُ��x�������u�����v�A�ǂ�ł݂Ă��������B�j
�y���܂��u��S�y�v�z
���[�������A�܂��Ȃ����~�Q�肪�n�܂�܂��B
�O�k�͕ʖ��u���E�y�i����ɂ�ǁj�v�Ƃ����܂��B
�����͎l�ꔪ�ꂤ���܂����E�̐��E�ł��B
�S�͔߂��݂�ꂵ�݁A�Y�݂�s���Ɋ����A
�̂͊����E�����E�ЊQ���ɑς��E�Ȃ���Ȃ�܂���B
�N�X�����Ȃ邨�~�̎����B
���Q��Ɍ������Ȃ���A���ސg�́B
���E�y��g�������Ēm�炳��܂��B
�������Ƃɓ���ƁA
�����ɂ͎��[����̂悤�ɂ��ꂢ�ɏ���ꂽ�����d������܂��B
���[����ɂ͈������Ȋ肢�����߂��Ă���悤�ɁA
�����d�̂�����ɂ������܂̊肢�����߂��Ă��܂��B
�Ƃ̕�������܂������A
�ł����̂͂���y�̑����A
�����܂̊肢�łł�������������y�̗l�q�ł��B
��S�����i���傤����j�Ƃ����A
�̂ɂ���y���u��y�i����ǁj�v�Ƃ������܂��B
�����Ĉ���ɂ��܂̊肢�́A
���̛O�k�ɂ��鎄�ɂ�������͂��Ă��܂��B
��\����̂��{��A
�u���O���~�������ł��Ȃ���Ύ��͕��Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�B
����y�ɂ��̎��܂ꂳ���Ȃ������y���J�����Ӗ����Ȃ��A
������������镧���܁B
����y���J���ꂽ�̂͑��Ȃ�ʎ��̂��߁A
����Ȋ肢���̂����O���ł��B
�����E�Ԏ��������E�Ƃ����Ӗ��ł��̐��́u���E�y�i����ɂ�ǁj�v�ł��B
���������O���ɂł������A
���̐��͔@���̊肢�S��t�̐��E�Ƃ����Ӗ��Łu��S�y�i����ǁj�v�A
���̂悤�ɌĂ��Ă��������܂��B
�O�k�̊��E�y�Ŋ����A
��������S�y��������������A
����Ȃ��~�̋G�߂ł��B
�i�����j ���`����
���ɐ�����
�y���m�炸�z
����A�j���[�X�ɂ���ȋL�����B
�u�A�����J�̃g�����v�哝�̂ƁA�C�[�����E�}�X�N�������݂������R�Ɣ��v
���̗ǂ������Q�l�����_�����Ƃ����̂ł��B
�����͂Ƃ������A���̌��_�Ń}�X�N�����������̂��A
�u���������Ȃ���g�����v�͑I���ɕ����Ă����i�����j���ĉ��m�炸�ȂB�v
���́u���m�炸�v�Ƃ������t���C�ɂȂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA
�����́uSuch ingratitude.�v�B
�uingratitude�v�́u���Ӂv������킷�ugratitude�v�ɔے莌�uin�v�������P��ł��B
���肩��̎v�����≶�b��Y��A���ӂ̂Ȃ����A���ꂪ�u���m�炸�v�ł��B
�ŋ߂��܂蕷���Ȃ��u�����v��u���m�炸�v�ł����A
�A�����J�l���狳���Ă��炢�܂����B
�y�ڒq�z
���Ƃ����A�~�J�̂��߂��߂������̍��Ɏv���o�����b������܂��B
����͏��w�Z�̍��ɓǂb�ł��B
�������Ɂu���ザ��i�ˎ�j�ǂ�v�i1584�`1634�j�ƌĂ��w�̒Ⴂ�l�����܂����B
�啪�̋g�l�Z����A�F�{�̕F�s����Ɠ������A�ڒq�̍˂�����܂����B
���鎞�A�a�l�̂����ő���ɂł����܂����B
�r���ʼnJ���~��o���܂��B
�J��̗p�ӂ����Ă��Ȃ������̂ł����A
�a�l�͑������߂܂���B
�Ɨ������͍����Ă���ƁA�ˎ�ǂ����������̂ł����B
�@�u�ǂ������̂���B���ł��ɂ��Ȃ��������v
�@�u�������a�B���Ȃǒɂ݂����ʁv
�@�u�ł́A���̂��̂悤�ɋ����Ă���̂���v
�@�u�a�A������������������B���͂��̘ˎ�A�����قǐe�̉��̂��肪���������������Ƃ�������܂��ʁB
�@���Ƃ����肪�����āA���肪�����܂����ڂ��Ă���̂ł���������v
�@�u����́A���S�Ȃ��Ƃ���B�����A�܂��ǂ����č����Ɍ����āA����Ȃɐe�̉��ɁA���肪�����܂����ڂ��̂����v
�@�u����͓a�B���̒ʂ莄�̐e���A���̕@����Ɍ������ɉ��ɂ��Ă��ꂽ�������ŁA�ǂ�ȂɉJ���~���Ă��A�J�����@�̒��ɗ��ꂱ�݂����ʁv
�@�u���ށA�Ȃ�قǁv
�@�u����͊F�A�e�̂������A�e�̉��ł���������B�����v���Ƃ��肪���ɁA�܂����ڂ�ĂƂ�������ʁv
�@���������Ęˎ�ǂ�́A�Ȃ��������肠���ċ����̂ŁA�����̐l�������������Ō����܂����B
�@�u����ˎ�ǂ�B�������@�̌����炢�̂��ƂŁA���������Ƃ́A������Ƒ�U��������킢�v
�@�u�������@�̌����炢�Ƃ́A�����̂ĂɂȂ�����ʁB���̂��肪������������ʂƂ́A�e�X���̕@�́A���Ă͏�����ɂ��Ă���̂ł́c�c�v
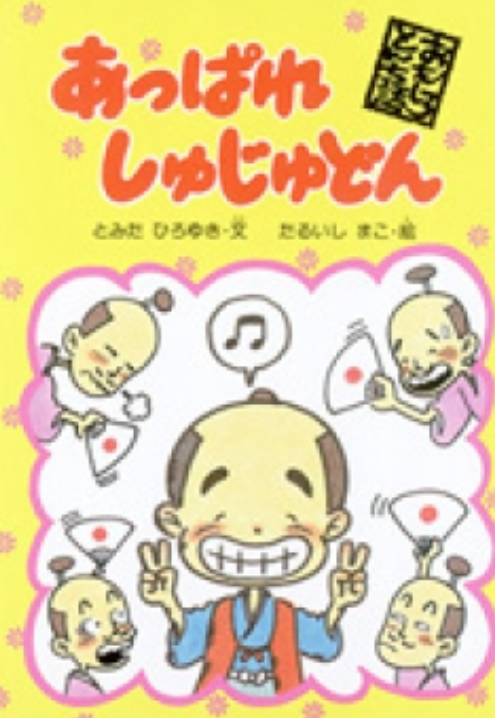
�@�ˎ�ǂ�́A�����̐l�����̊�������ƌ��߁A
�@�u���ꂼ��e�X���̕@���A�݂ȉ������ɂ��Ă�������B���A�ʼnJ�����@�̒��ɗ��ꍞ�܂��ɗ��ꗎ���Ă������v
�ƁA�^�ʖڂȊ�Ō����܂����B
�@�u���ށA���������B�ˎ�̌����������Ƃ��ȁv
�@�J�̒��łʂ�˂��݂ɂȂ��������̎҂��������Ȃ���a�l�������܂����B
�@�u�F�̎ҁA�����n�����������B�e�̉��ŕ@�̌��͉������ɂ��Ă����Ă��A�����G��Ă͂��Ȃ�ʂ���̂��B
�@�n�b�n�b�n�B�܂��ˎ�ɂ��ꂽ�킢�v
�@�a�l�͏��ƁA����������߂���ɋA���������ł��B
�i�y�c���V�w�����ςꂵ�ザ��ǂ�x, pp.52-63�B���X��A�Ђ炪�Ȃ������ɕς��܂����j
�i�w�����R�ˎ�Y���x�i54-56�Łj�ł͓��e�������قȂ�j
�y�悤�����悤�����z
�ˎ�ǂ�͓a�l��������邽�߂Ɂu�@�����Ɍ����āv�Ƌ����܂����B
�Ƃ���ŁA���̕@�̘b�Ɠ��������������l�����܂��B
���D�l�i�݂傤�����ɂ�j�̌����i���Ȃ̂��j����ł��B
�i���D�l�Ƃ͂��O�����ϊ�ꂽ�l�̌h�̂ł��B�j
1842�`1930�N�A���挧�̐l�ł��B
18�̎��A�������S���Ȃ�A
�u���炪����A�e�l�����̂߁v�̈⌾�������ɂ����Q����n�߂܂����B
�ŏ��͂Ȃ��Ȃ�������̉��i��傤���j�A�������������ł��܂���ł������A
���鎞�̎d���̋A�蓹�A
�d���Ȃ����̂Ŏ����Ă��������̑��������ɒS�������u�ԁA
�u�ӂ����ƕ����炵�Ă�������v�A
�̉��ł����Ƃ����b�͗L���ł��B
����Ȍ�������Ɏ��̂悤�ȃG�s�\�[�h������܂��B
�[���ɂł����������A�S�g�ʂ�˂��݂̂悤�ɂȂ��ēc�ށi����ځj����A���Ă��܂����B
���̂��������݂������������̏Z�E���u��������A�悤�ʂꂽ�̂��v�Ɛ���������ƁA
�ӂ�ނ��������́A���Ԃʂ�̊���ق�����Ȃ���A
�u���肪�Ƃ������A��@�Ƃ���A�@�����Ɍ����Ƃ�ŗL����Ȃ��v
�Ƃ����������ł��B
�i������w���D�l�̂��Ƃx123�Łj
�u�悤�����悤�����v�����Ȃ̌�������B
���������������ɂ������ӂ���邨�O���҂ł����B
�u�@������͓̂�����O�v�A
�u�����Ă���͓̂�����O�v�A
�u�H�ו�������͓̂�����O�v�A
�����ے�͂��܂��A
�����������ł͂Ȃ������Ƃ��������鐢�E������܂��B
���O���̐��E�ł��B
�y����̓]��z
���O���́A�~���悤�̂Ȃ��҂��~����^���̘b�ł��B
���̎��ɂł��������A����͂���Ӗ��A
���ł��Ȃ��Ǝv���Ă�����������ςȒl�ł����Ɍ����Ă��܂��B
�����Ăǂꂾ���h���A�܂����炵�������ɂ����A
���ӂ���Ƃ������������܂��̂ł��B
�u���̏�̖̏��͂�����Ӂv�ƌJ��Ԃ��ꂽ�@�@��l�ł��B
���O���͊��Ӂigratitude�j�ł��B
�킪�g�̍߂�ӂ߂���A���l�̍s�ׂ����O�ɁA
������ӂɂ��Â����O���ł��B
���C�Ȃ����̏u�ԁA
��ςȂ��������������������Ċm�F�����Ă��������܂��B
�����ɂ����ĊJ���ꂽ���n�́A�����Ă�����_��I�ȋ��n�ł����ł��Ȃ��B
����͌��ǂ�����܂��̂��Ƃ�������܂��̂܂e���Ƃ���ɂ���B
�l�̋ꂵ�݂͖{�����̂�����܂��̂��Ƃ�f���Ɏ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���ɂ���B
���������̌����͂���ꎩ�g�̂����ɂ���B
�����̌����u�ӂ����ƕ����炵�Ă�������v�Ƃ������Ƃɂ́A
���������t�]�I�E���{�I����̓]����B
�����āu�悤�����悤�����v�Ƃ������t�ɂ́A������������̓]��ɂ����ĊJ���ꂽ�����̒��O�̐��E������B
�i�����N�v�u�悤�����E�����v�i�w�R����w�N�w�����x10, pp.1-20., 2001�j
�i�����j ���`����
�Y�����́E�Y��Ȃ�����
�y��Y��z
�������������Y����ۂ��A�悭���s����l��e���҂Ƃ����܂��B
����ɂ͂���ȑe���҂��o�ꂵ�ď킹�Ă���܂��B
�u�e���̎g�ҁv�Ƃ������b�ɏo�Ă���e���ҁi�g�ҁj�́A
�s������ŗp����Y��܂��B
��������G���}�i�B�����j�ł˂��āA
���̂��܂�̒ɂ��ʼn��Ƃ��v���o���̂ł����A
�u�c�c�������ɎQ�����B�v
�Ƃ����T�Q�ŏI���܂��B
�u�e���̓B�v�Ƃ������b�̑e���ҁi��H�j�ł́A
�e���҂������z������̕ǂɁA�����B��ł�����ł��܂��܂��B
�u�B�����ׂɔ����o�Ă邩������Ȃ���I
�ӂ��Ƃ��ŁI�v�Ɖ�����ɂ����A
����Ăē��������̉ƂɊm�F�ɍs������A
�u�������ȁI�v�Ɖ�����ɒ��ӂ���āA
�ׂ̉Ƃł͗������������āA�S�R�Ⴄ�v�w�̂Ȃ肻�߂̘b�����ċA���Ă�����B
�悤�₭���ׂ̐l�ɓB�̎���b���Ē��ׂĂ݂�ƁA
�Ȃ�Ƃ��ׂ̂����d�̒����璷���B�����o�Ă��܂����B
���ׁu�ǂ������ł��I�v
�e���u����[�A�����͂ǂ����s�ւ��ȁB�v
���ׁu�Ȃɂ��H�v
�e���u����A�������������Ƀz�E�L�������ɂ��Ȃ��Ⴀ�����Ȃ��B�v
���ׁu��k����Ȃ���I�v
�c�c�Ƃ����āu�e���̓B�v�͏I���̂ł����A
���̗���A������������������܂��B
�u�������܂��A���Ȃ����������������ł��ȁB
���ׂɂ����Ă�����ł����B
�ǂ��炩��H�v
�u�����̕�����ł��B�v
�u����ł��Ƒ��͉��l�H�v
�u�͂��A�������ƃJ�J�A�Ƃ������̐e����l�����ł��B���ꂳ��B�v
�u���ꂳ����B�v
�u�����ˁI�@���ꂳ��A�O�̉Ƃ̓�K�ɒu�����ςȂ��ł���������I
�܂����ȁA�����ɖ߂�Ȃ���I�v
�u�c�c���Ȃ��A�������������ɂ���������܂���B
�e��Y�ꂽ��ł����I�v
�u����[�A�e��Y���ǂ��낶��Ȃ��B
���傢�ƈ�t�ۂނƁA���Y��܂��B�v
����ȃT�Q�ŏI���ƁA���ږ����u��Y��v�ɂȂ�̂������ł��B
�y���̂��Y���z
����������ʼn��Y��āA
�����̎����b������A�l�̈����������l�A���X�������܂��B
�Ƃ���Ŋo�@��l�̐e�a���l�������w�u���x�Ƃ��������ɁA
���̌��t������܂��B
������ɑc�t���l�i�e�a�j�A
���S�M�y���̂��Y����A���݂₩�ɖ��s�s���̊�C�ɋA��
���O�̖����i�����j�݂���ĂƂ����Ȃւɕs�f���ӂ̌��v�Ɋցi�������j��B
�e�a���l�͈���ɂ��܂̂��{������������܂����B
���̖������݂����u���̂��Y��v�܂��B
���������Ԃ̂悤�ȋ��M�ł͂Ȃ��h�M�i���傤����j�ł��B
�����A�������͕������q�ϓI�ɁA�����I�ɂ݂Ă������ł��B
�ł����A�ǂ����Ă��������S�I�Ȃ��̂̌����ɂȂ肪���ł��B
�����ĕ��@�A�����܂̘b�������̓s���悭�����Ă��܂��̂ł��B
�u����Șb�͂킩��܂���v�Ƃ��A
�u����͂܂�A�����͂������Ȃ�������Ȃ��̂��v�Ƃ��B
�����̕�������e�łƂ炦�悤�Ƃ��܂��B
�����Ă���悤�ŕ����Ă��Ȃ��̂ł��B
�u���̂��Y���v�Ƃ́A
����Ȏ��͐S���Ƃ�͂��ꂽ��ԁA
���̍����ɐ��������Ƃ����͂��炫�ɐS������ꂽ��Ԃł��B
�ϔY�ɐU�藐�������X�̎������ł��B
����̗l�X�Ȏ����ōl���Y�݁A�����܂̎��͖Y�ꂪ���ł��B
�܂��A���c�n�C�}�[��F�m�ǂɂȂ��Ă��܂��A
����ɂ��܂̎��͂�������Y��Ă��܂���������܂���B
�����������炪�Y��Ă��A
����ɂ��܂̕�������Y��Ă����܂���B
�̂̐l�́A����ɂ��܂��u�e�l�v�ƌĂт܂����B
�q�̎����e��Y��Ă��Ă��A
�e�̕��͕Ў����ڂ𗣂������Ȃ��̂ł��B
�y2�̗ՏI�z
�����炪�e���҂ł�����ɂ��܂��������肵�Ă��邩����S�Ȃ̂ł��B
�ł�����������̂́A
�u����ɂ��܂����ł�����Ȃ�A����Ƃ��Ă����S���v
�Ƃ������������̒��Ɋ_�Ԍ�����A
����Ȏv�����݁i���͐S�j���������A
����ɂ��܂̂��S�A���{����Ă��邩��{���̈Ӗ��ň��S�Ȃ̂ł��B
�i����ɂ��܂͈���Ƃ����̂����������Ƃ͂���܂��A
����Ƃ������ق߂Ă͂����܂���B�j
�c�c�����܂ŁA���Ƃ��b�ł��B
��������A���悢�摧��������鎞�ł��B
�Ƒ�������Řb���Ă��܂��B
�u��������A����J�l�������ˁB
�h�����ǂ��낻�남�ʂꂩ����B
��������A�ǂ��ɂ������Ⴄ�낤�B�v
�����ŁA���̕����ڂ��o�܂��܂����B
�u�����I�v
�u��������I�v
�u�v���o�����I�v
�u���H�v
�u�c�c�������ɎQ�����B�v
���������ꍇ�A�u�e���̎g�ҁv�ł͂Ȃ��A
�e���̎��҂ƌ����̂�������܂���B
�i�����܂ŏ�k�A���Ƃ��b�ł��B�j
�c�c���ɂ�����A����Ȃ��b���܂����B
�l���Ō�ƂȂ���������ɁA���������܂����B
�u���Ȃ��A���܂ł���J�l�B���܂Ŋy���������ł��ˁB�v
�u�������ˁB�c�c�ł��A�����y������B�v
�u�c�c�c�c�����ł����ˁB
��������ɂ��܂̐e�l�̒��B
�����Ă��ꂩ�爢��ɂ��܂̂�����A
�e�a���܂�������A����y�ɋA�点�Ă��炤�̂ł����ˁi�܁j�v
�e���ȏ����������ł��B
���܂����͂̂��@�`�����`���ł��܂��A
�N���������ɂȂ�O�A�������I����O�ɁA
���@�̂����ɂ����A
�u���̂��Y��āv���O�����Ă�������A
�ꏏ�ɂ���y�ɎQ�肽���Ɗ肤���ł��B
�i�����j
���ւ̂��Ƃ�
�y���ւ̒��z
�u�ёы��̒����킭�Ɂv�u�ČR��n�̂��钬���킭�Ɂv�A
����Ȋ⍑�s�́u���ւ̒��v�Ƃ������܂��B
���ւ̓A�I�_�C�V���E�̓ˑR�ψَ�ł��B
���E�I�ɂ��߂��炵���炵���A
���������A�ڂ��Ԃ��A���̓V�R�L�O���ł��B
���悻300�N���O�ɔ������ꂽ�⍑�̃V���w�r�B
���Òn��ő�ϔɐB���܂����B
���݂͂قƂ�ǂ݂����鎖�͂Ȃ��Ȃ�܂������A
�u�⍑���֕ۑ���v�ɂ���ĉ����Ŗ�1000���قǎ��炳��Ă��܂��B
�ёы��߂��́u�⍑�V���w�r�̊فv�ł��ł��ς邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�w�r�Ȃ�ċC���������v
�ł��ĊO���킢���ł���B
�y�ւ̏́z
�������������̂����ōł��Â����T�u�X�b�^�j�p�[�^�v�B
���̑��́u�ւ̏́v�Ƃ����܂��B�`���̎����A
��@�ւ̓ł��i�g�̂̂��݂��݂Ɂj�Ђ낪��̂��Ő�����悤�ɁA�{�肪�N�������̂𐧂���C�s�ҁi��u�j�́A
���̐��Ƃ��̐��Ƃ��Ƃ��Ɏ̂ċ���B
�\�\�ւ��E�炵�ċ�������̂ċ���悤�Ȃ��̂ł���B
���{�l�����܂�D�܂Ȃ��w�r�ł����A
��A�W�A�ł͑�ςȂ��݂̂���e���݂̂��鐶�����ł��B
���̃w�r�̒E��̂悤�ɁA
�C�s�҂͏C�s�ɂ���ď��X�̔ϔY�𐧌䂵�A�����̍��{�ł��鎷���S��E������܂��B
�y�E��z
��y�^�@�͕����̒��ŏ�y��Ɉʒu���܂��B
����ɕ��̖{���M���A�O�����ď�y�։������铹�ł��B
���̏�y�^�@�A���̑����̏@�h�̂悤�ɔ�����Ƃ����������܂���B
���������Ă��܂����A�������H���܂��B
�����ĉ������C�s������A�P����ςނƂ����s�ׂ����܂���B
�������ł��u������ς߂Ύ��R�ɗǂ����������Ă���v�Ƃ͐����܂���B
�u��y�^�@�͖{���ɕ����Ȃ̂��H�v
�u�����炵�����i�C�s�j�����Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����B�v
�u��y�^�@�́A��y��̓ˑR�ψَ킾�B�v
����Ȑ����o��̂�������Ȃ�������܂���B
�e�a���l�͔�b�R�Ő^���ȕ����C�s����܂�܂����B
�������ϔY�𐧌䂵�悤�ɂ��A���܂ꎝ�����Ŏւ̂悤�ɁA
������ł��~�]�E�{��E��s�Ƃ������ϔY���N���N����}�v�̂킪�g�ł��B
�E���͂悭�Ȃ��̂͒m���Ă��܂��B
����ǂ��ǂ����Ă����̂��̂����Ƃ�Ȃ���ΐ������܂���B
���̂��̂��̋]���Ȃ����Ď����̂��̂��͐������܂���B
����Ȑg�̏�ɂ������ꂽ���̋���������ɂ��܂̖{��̋����ł��B
���͂̔O���҂͕��@��ʂ��đ��͂̐M�S���l�����A�����̖W�����鎩�͐S��E������܂��B
�P����t�́u��͔����v�̂��Ƃ����o����܂����B
�u���̂܂ܗ�����A�K���~���v�Ɗ��Ԉ���ɂ��܂̐����A
�ϔY�̊C�ɂ����Ǝ����ꂽ����ɂ��܂���̐���Ȃ锒��������܂��B
�ւ͉��x���E�炵�܂����A
��y�^�@�̒E��͈���A
�M�S�l���������̈�O�̎��A������y�����̓��͌��܂�܂��B
�ł����炠�Ƃ̕����́A������ӂ̐����ł��B
���ꂼ��g�̏�ɂ������@����Ԑ����ł��B
�u�Չ������l�v�i��y�ւ͉����₷������ǂ��A���̓�����ގҁA���͂̐M�S�����������҂͂܂�ł���j
���͂̂��O����̐l������ސl�B
����͑�ϋM�d�Ȑl�ł��B
������������V�R�L�O����������܂���B
���݂����O�����ɂ��������̂ł��B
�y���N�̍~�a��z
���N�͂ւєN�A���̔N�ł��B
������5���͗��āA���̌��ł��B
���N�̖�����5��21���͖��N���܂�̐e�a���l�̂��a��������ԁu�@�c�~�a��v�ł��B
���N�͂��a��852�N�ł��B
�Ƃ���ł��̒a���́u�a�v�A
���Ɂu���v�Ə����܂��B
���́u���t�����т�A�E�\�E�����v�Ƃ����Ӗ������邻���ł��B
���̐��ɐ��܂��A�l�Ԃ̐��E�ɐ��܂��Ƃ������́A
���@�ɂł����Ƃ����Ӗ��ŁA�ɂ߂ē����������ł��B
���������̐��E�͎�����H�A�����āu�����s���v�ł��B
�G�C�v�����t�[���iApril Fool�j�͔N��1�x�A�E�\�����ėǂ����ł����A
���ۂɂ̓E�\�̂Ȃ����Ȃ�Ĉ�x������܂���B
�������\�̓d�b�͖苿�����A
���Ȃ�ʎ��̐S���{�̂悤�Ɂu�R�P�R�P�i�����j�v�Ɩ苿���Ă��܂��B
�^�ʖڂɐ����悤�A�����������悤�A�D���������悤�c�c�ł������͂����Ȃ������B
���������Ƃ��݂Ȃ����ʂ炸�A�E�\�E�����ƂȂ鎄�B
����Ȏ��̃E�\�̐��E�ɉ���Ă��Ă����������e�a���l�A
��و���ɕ��Ƃ킪�g�ɖ苿�������܂��������������܂����B
����āu�~�a�v�ƌ����܂��B
�w�r�͒E�炷�邪���Ƃ��A
�e�a���l�̂��a���������ɁA
�����S��E������͖̂����ł��A
���͐S��E�����邲���A
���@���n�߂�V�������̂����a�����鎖���肤����ł��B
�a�������l�Ԃ̋��E�͋��̓��ł����A
�����ւ̈�{���ł��B
�֑��Ȃ��A�Ë��Ȃ��e�a���l�̌��t������ɁA
�@�c�~�a��������ɁA
����k��l��l�Ƃ��O���̓������ł܂��肽���v���܂��B
�y�lj��F5��21���z
����ƍ����̐꓿���̍~�a��B
��N90�̒����搶19��ڂ̑������@���ł����B
�����ߌォ��͂j����̂����V�i���͑O�������V�j�A
�܂������搶�ɂ��Ƃ炸���x�����o�������������v�搶�̌䉝���A
����ɖV��̕��̐e�F�s�搶�̂������S�ĂƂ̃j���[�X����э���ł��܂����B
�Ԓf�Ȃ�����̕����v���m�炳��܂��B
���V�̌�̉Α���A
�u����͂ɂفv�Ɣԍ������ԘF�O�B
�ӂƁu�����������v�앶�������т܂����B
���@����ɂ���
���@������Y��
���@�L��̐g
���@�����肪����
���@�����肪����
�j����A�v����A�s����̘b�ł͂���܂���B
���т�������̐l���͑��Ȃ�ʎ��ł��B
���͉����̔����͂ǂ����ɂ���̂ł͂���܂���B
���ւ̂��Ƃ��A�����͂킪�g�ɂ�����͂��Ă��܂��B
�i�����j ���`����
���w����
�y�ω��z
�����ɂ�����@���������u�����v�Ƃ����܂��B
�O���������������ƁB
���l�╧�@���^����������̂ȂǁA
������l��^���̋����ɓ�������邱�ƁB
�i�w��y�^�@���T�x�u�����v���j
�w��o�x�ɂ͈���ɕ��̊����Ƃ��āA
�����̏O�����������Ĉ������āA���㐳�^�̓��ɏZ�����ށi���ߔ�27�j
�i�y������z������Ȃ��l�X�����������A���̏�Ȃ����Ƃ�̐��E�Ɉ��Z�������B�j
�Ǝ�����Ă���܂��B
�����邢�̂��̎҂������������B
����ɂ���đ��͂̐M�S���������������ʁA
��ꂤ�����S�������܂�A���̂��Ƃ�̓�����ގ҂ƂȂ�܂��B
���ꂪ�����̗��v�ł��B
�e�a���l�́u�w���x�͂��Â̂��̂𗘉v���Ɩ�v�i�����^�������j�Ɛ�����܂����B
���������Ƃɂ���āA
��������ސg�ɕω����鎄�����ł��B
���O��������g�ɕς������A
�����Q��̐g�ɕς������A
�����d���ɂ���҂ɕς������A
�l�ɂ���Ă��̕��ӂ̓x�����͂��܂��܂ł��傤�B
�������������܂��M�S�������������Ƃ������B
�����ڂɂ͕ς��܂��傫�ȕω��ł��B
�u���v�w�����������ł��B
���f�Ǝ_�f�Ƃ����C�̂��������Đ����ł��܂��B
�C�̂���t�̂ɁB
�傫�ȕω��ł��B
�y���[�����z
�f��w��ɗ����l�x�́A
���l�����鐼���~�i�C��ۈ�������h���̒����S���j�ɂ��A
1�N�ȏ�ɂ킽���ɑ嗤�u�h�[���ӂ���n�v�̑̌��L�ł��B
���̌Ǔ��Ƃ�����Ɋ��̒n�B
�����o�[8�l�͏��X�ɃX�g���X�����܂�܂��B
����ȏ𗿗��ł������ł��a�炰�悤�Ƃ��鐼������B
�Η͂̂Ȃ����ŃX�e�[�L���������A
�ɐ��G�r�ŊC�V�t���C���������A
�~�b�h�E�C���^�[�ՂɃt�����X�������������B
����ǂ��X�g���X�͂��܂�܂��B
���f�Ń��[������H�ׂ�l�����o���A
�f��̒��ՁA���Ƀ��[������������܂��B
�u���[�����͑łĂȂ��́H�v
�u�������Ɨ��͂����ł��傤�H�v
�u�����Ȃ���ł��B�v
�[��A�C�ے�����h���̋C�ۊw�ҁh�^�C�`���[�h�͗܂Ȃ���ɐ�������ɑi���܂��B
�u��������A�l�̑̂̓��[�����łł��Ă���B�v
�u���[�������H���Ȃ��Ȃ�Ɖ����y���݂ɐ����Ă��������̂��낤�B�v
���ꂩ��l�X�ȏo�����������āA�f��̌㔼�A
��X�w�҂́h�{����h�����C�Ȃ���������Ɍ����܂����B
�u�����N�A���͂��ɂ��Ă�����ƒ��ׂĂ݂����ǁB
�����������A�Y�_�K�X���܂��Ȃ��āB�v
�u�͂��B�v
�u�����N�����A�x�[�L���O�p�E�_�[���ĉ����H�v
�u�c�c�ӂ��炵���B�v
�u�i����ɂ͒Y�_���f�i�g���E���������ĂĂ邩��A�j
����ɐ������Ă݁B�Y�_�K�X�o�邩��B
����ɉ��Ȃ����ƌ���Ȃ����ɋ߂����̂ɂȂ�Ǝv����ˁB
�܂��A�����܂Ō��f�L���ł̘b�����ǂˁB�v
2NaHCO3�@��Na2CO3 + CO2�E H2O
�i�Y�_���f�i�g���E�����Y�_�i�g���E���{��_���Y�f�{���j
�����Ă݂�Ɖ��ƃ��[�������ł��܂����B
����H�ׂĊ�������h�^�C�`���[�h�B
�u�����N�B���[�������I�I�v
��S�s���ɂ�����o���܂��B
�����ցh������h�Ɓh�Z���h����э���ł��āA
�u�I�[�������ł��I
����Ȃ������I�[�����݂����ƂȂ��I�v
��������I
�^�C�`���[�I
�c�c�˂��^�C�`���[�H
�i�C�ۊw�҂Ȃ���j�ϑ����Ȃ��Ⴂ���Ȃ���Ȃ��́H�v
�u�I�[�����H
����Ȃ���m�邩�I�v
�y�M�S�̐g�z
�O�����������镧�̂͂��炫�ł��B
���̕��̔M�ɂ���ĉ��w�����̂��Ƃ��A
�傫�ȕω����N���鎄�����ł��B
�M�S��낱�Ԃ��̂ЂƂ�
�@���ƂЂƂ��ƂƂ����܂�
��M�S�͕����Ȃ�
�������Ȃ͂��@���Ȃ�
�i��y�a�]�A�������v�]�j
�}�v�̐g�ɂ��āu�@���ƂЂƂ��v�ƌ���قǂ̕ω��ł��B
�H�ׂ��͂��̂Ȃ������Ɋ��̓�ɂŃ��[�����ɂł������҂̂��Ƃ��A
����������͂��̂Ȃ��������E�y�̛O�k�ŐM�S�����������܂����B
���㖭�ʂ̐����������ɂ͂��炸�A
�^���̏�M�܂��Ƃɓ��邱�Ɠ�B�i�w��y��������x�A���ߔ�480�j
���蓾�Ȃ����Ԃ����������Ă���̂��A
���O�������������l���ł��B
�i�����j ���`����
��̂����
�y�Ղɂ�����́z
�n����̉Ƃɂ��Q��ɂ����܂����B
���߂̌�A���������������Ă���ƁA
�u���́A��N�O�ɑO�Z�E�����Q�肳��āA
���̋A��ۂɂ�������ꂽ�̂ł��B
�w�n����A�O�����ɂ͂Ȃ��āA�Ղɂ͂�����͉̂���������܂����H�x
�w�킩��܂���B�v
�w����͂ˁA�������i�Ձj�B�x
���������ďΊ�ŋA��ꂽ�̂ł��B
�����ɂ͌��Ă̒ʂ�A�Ղ�����܂��B
��������Č���ꂽ�̂ł��傤�B
�ł��Ȃ�����ȁc�c���Ȏ����B
�O�Z�E����Ɉ��C�͂Ȃ��悤�Ɍ������̂ł����A
�w�y�������i�Ձj�A�ʔ������i�Ձj�x�ł͂Ȃ��A
�Ȃ��w�������i�Ձj�x�Ƃ�����������̂��B
�Ղ̂��鎄�̉Ƃ͕s�K�Ȏ���������Ƃ����̂ł��傤���B
��N�ԍl�����̂ł����A������Ȃ���ł��B�v
�u�����܂���A����������܂���̂Ŗ{�l�ɕ����Ă݂܂��B�v
�Ƃɖ߂��đO�Z�E�ɂ����˂܂����B
�u�c�c�Ƃ����킯�łn����͂��̈�N�A��X�Ƃ��Ă��������ł���B�v
�u����A����͈��������B
�ł�����͌���ł��B
�����͏�k�����������肾�����̂��B�v
���Ƃ������̂��Ƃ����ƁA
�n����̉ƂɋՂ�����̂����āA
�u�n����A�w�O�����̂Ȃ��Ƃ͂����Ă��A�Ղ̂Ȃ��Ƃ͂Ȃ��x�����ł���B�v
�u�ǂ������Ӗ��ł����H�v
�u����͂ˁA���ߎ��i�Ձj�B�v
�T����݂�Ή����Ȃ��l�q�݂��Ă��A
�ǂ̉ƒ�ɂ��l�X�ȑ��l�ɂ͂����Ȃ��������܂��B
��Ȃ菬�Ȃ���ߎ��E�Y�ݎ��̗ނ�������Ƃ����Ӗ��ł��B
�����炭�O�Z�E�͂n����̔Y�݂��āA
�u�Y�݂̂Ȃ��ƂȂ�ĂȂ��ł���B�v
����ȗ�܂��̈Ӗ��ł��̎����������̂ł��傤�B
�Ƃ��낪�A
�u�O�����̂Ȃ��Ƃ͂����Ă��Ձi���j�̂Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v���A
�u�O�����ɂ͂Ȃ��āA�Ղɂ͂�����́B����͈������v�ƁA
�����ԈႦ��ꂽ�̂ł��B
���܂��`����Ă��܂���ł����B
�y���������z
�S���P�T���́u�����J�@�L�O���v�ł��B
��y�^�@�̋���������킳��A�@�h���J���ꂽ���Ƃ��L�O������ł��B
�c�c�u�����̂Ȃ������v������܂��B
�^��Ƃ��킭�A�ǂ��������u�A�N�V�f���g�ł��胆�[�����X�v�ȓ��{�̕����ł��B
��y�^�@�͐�Α��͂̋����ł��B
����ɗl�̈�l���炫������ꂽ�e�a���l�ł���A
������ł��邩����_���I�Ɏ����ꂽ�e�a���l�̒��w���s�M�x�ł��B
�����ő�ɂȂ�̂��u�������v�ł��B
���͂̋����́u���O����v�Ƃ��u�M�S��v�Ƃ��A
�����āu������v�Ƃ������܂��B
�������čs������ȑO�ɁA
�����𐳂��������i�M�S�����������j�����̗v�ł��B
�t�ɂ������̋����A
�悭�����ԈႦ��̂ł��B
�u��y�^�@�͕s�^�ʖڂ��B
�w�ǂ̂悤�Ȑ����������ׂ����x�Ȃ�Đ������A
��k����b�������B�v
�@�b�͗���Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�z���g�͕s�^�ʖڂɏ�k����b�����Ă���̂ł͂���܂���B
�^���ɑ��̖͂@�`��`���悤�Ƃ��Ă��܂��B
�u�������Ȃ��ėǂ��Ƃ́A���Ƃ��������ȋ������v�ł͂Ȃ��A
�u�����������p�ӂƂ́A���Ɩܑ̂Ȃ������B�i�����܂Ɂj����J�����܂����B�v�ƁB
�u���Ƃ��Ă��~���v�Ɛ���ꂽ�����܂̖{�S�ɐS���������̂ł��B
�y�w�т̂���l���z
�����������ɂ����y�^�@�ł��B
�����u�����v�ƕ����Ɓu����v�u�w�Z�v�ƘA�z���A���ꂵ���C���[�W�����l������悤�ł��B
�u�����Ƙb���Ȃ����I�v
�u�����Ȃ��̂Ȃ�A�����܂Řb�������邼�I���Ƃ���߂Ȃ����I�v
����Ȍ����������搶�̐h�����ƁB
����������Ȃނ������͖@���ɂ���܂���B
���ԂɂȂ�����I���܂��B
�o���Ȃ���~���Ȃ��b�ł͂Ȃ��̂ł��B
�������́A�M�S�����������A�@���̂����߂ɂЂ������B
���ꂪ��y�^�@�́u�w�сv�ł��B
�����Ă��O���������ł��B
��������ł��������Ȃ������A���A
�@���̉i���̌��̒��ɕ�܂�Ă��܂��B
���ߎ��E�Y�ݎ������Ȃ����A
�l�X�Ȏ�������������������ł��B
���������Ƃ͂����܂���B
���������ɁA�@�������i���Ƃ��j�ɂł����܂��B
�����āA�����ł͂Ȃ��u�厖�i�������j�v�ƕ����܂��B
�u�㐶�̈�厖�v���A
�@���̂����������̂��S�ʂ�ɕ������A
�������@�����܂Ƃ́u��ԑ厖�ȍ����̈���v�ƂȂ�܂��B
�u�w�O�����̂Ȃ��Ƃ͂����Ă��Ձi���j�̂Ȃ��Ƃ͂Ȃ��x�B
�킪�Ƃɂ��Ղ�����܂��B
��������̔Y�ݎ�������܂��B
�����킪�Ƃɂ͗�i���j������܂��B
�����d�ɂ����i���j�ł��B
�����������d�ŗ��ł��A���߂��A���O�����A��������܂��B
�����Ƃ͂����Ȃ��l���ł����A
�����߂Ƌ��ɂ���厖�Ȑl���ł��B�v
������O�A
���������ɂܑ͖̂Ȃ��قǂ̌������A
���O����ʂ��Ēm�炳��܂��B
�w�т̑����l���͖L���ł��B
��y�^�@�ɗ����J�@�����������ƁA
�w�Ԃׂ����������i�@���̂ЂƂ���炫�j����������������Ă��������S���P�T���ł��B
�i�����j ���`����
�֑��̂Ȃ�����
�y�֑��z
���N�͂ւєN�ł��B
�����Đe�a���l���ւєN���܂�ł��B
�ւєN�Ƃ����Ύv���o���̂��u�֑��v�Ƃ������b�ł��B
�u����l���Ɨ������ɁA��t�ɐ����������ӂ�܂����B
����ƉƗ������́A���l�ň��瑫��Ȃ����A��l�ň��炠�肠�܂�B
�ЂƂA�n�ʂɎւ̉�������āA��ɂł������̂����ނƂ��悤�A�Ƃ������ƂɂȂ�A
��l���܂��悫�����A�����������Ƃ��č���ɔt�������A
�Ȃ��]�T���݂��āA�������ĉ悫�����邼�Ƃ���A�����悫�Y�����B
���̂����ɂ�����l���ւ��悫�����A���̔t��D���Ƃ�ƁA
���Ƃ��Ǝւɂ͑��͂Ȃ��A�����悫�Y������ւł͂Ȃ��A
�Ƃ����āA���̎�������ł��܂����Ƃ������Ƃł��B�v
�i�ђ˘N�w�����̎��x���i�p��I��71�j���j
���̂��b����u�֑��v�Ƃ́u�t��������K�v�̂Ȃ����́B���p�Ȓ����v�Ƃ����Ӗ��ŁA
���Ƃ��Ή�b�̒��ŁA�u�֑��ł����c�c�v�Ǝg���܂��B
�u���p�Ȓ����v�Ȃ猾��Ȃ���Ηǂ��̂ł����B
�y���͂̑��z
��y�^�@�́u�얳����ɕ��v�̂��O����̂����ł��B
����������Ƒ��͂̋����ł��B
���ɉ�������܂���B
�Ƃ��낪���̋����ɖ��ȁu���v����������̂��������ł��B
���͂̑��ł��B
��̓I�ɂ����A�O�����̂��Ȃ���
�u�i�����́j������ςނ��v�ƍs��������A
�u�i�����́j������ςv�Ɗ��B
�u�����P�v��ے肷�����͂���܂���B
����������Ƃ��O�����������Ă͂Ȃ�܂���B
�y�����ĂȂ��z
���̌����͌��ǁA�ŏ��́u�����v�ɂ���܂��B
�u�얳����ɕ��v�̋������Ă���悤�ŁA
���͕������Ă��邾���ŁA�����ĂȂ��̂ł��B
�i�z���g�j�u�@����F�������݉����Ƃ������ɂł����܂����B�v
�u�͂��͂��A�@����F�ł��ˁB�v
�i�z���g�j�u�����ł����镧�̍����݂��Ă��炢�܂����B�v
�u�͂��͂��A�݂��Ă��炢�܂������B�v
�i�z���g�j�u���̏�Ȃ��肢�����Ă邽�߂Ɍ܍��Ƃ��������Ԏv�Ă���܂����B�v
�u�͂��͂��A�l�����̂ł����B�v
�i�z���g�j�u�����Ăǂ̂悤�Ȏ҂����炳���~�����{������Ă��܂����B�v
�u�͂��͂��A�肢�����Ă���ł��ˁB�v
�i�z���g�j�u�{��𐬏A���邽�߂ɉʂĂ��Ȃ��������܂�܂����B�v
�u�͂��͂��A�������ꂽ��ł��ˁB�v
�i�z���g�j�u�얳����ɕ��̖��̕��ƂȂ��Ăǂ̂悤�Ȏ҂��ۂߋ~���A������y�ɐ��܂ꂳ������̕����܂ł��B�v
�u�͂��͂��A�ǂ�Ȏ҂��~�������܂Ȃ�ł��ˁB�v
�i�z���g�j�u�c�c�����Ă܂��H�v
�u�͂��͂��A�����Ă܂���B�v
���Ԃ��Ă܂���B
�u����ɂ��܂Ƃ��������āA��y�Ƃ��������āA���ǎ��͂��厖�Ȃ�ł���v�Ƃ���������ς��A
�������́A
�u����ɂ��܂Ƃ��������āA��y�Ƃ��������āA���Ǒ��͂Ŏ���̘b�ł���B
���̎��͎����ł��Ȃ��Ɓc�c�v�Ƃ����������_�ł��B
������������������Ȏv�����������Ă��鎨���ӂ����A
���̌��ʁA�u���͂̑��v�A�����̒��ł��O���ɗ]�v�Ȃ��̂�⑫�����Ă��܂��̂ł��B
�u���O����v�Ƃ́A���ꖞ���ł��܂���B
�y�X�|�b�g�j��z
�u���̐́A���������̏Z�ދߏ��Ɍ������ł��܂����B
�Ƃ��낪���炭����Ƃ����ō��܂���Ƃ����������E���̂������B
����Ő肢�t�ɂ����˂�ƁA�����́g��l��h�Ƃ����āA
���č���ő����̐l���Ȃ��Ȃ�A���̐l�����𑒂����ꏊ��������ł��B�v
�@���̌�A����Șb��M�S�ɂ������������܂����B
���Ԃ�A�����̕s�K�����������A���킸���F��₨�D���w������鎖�ł��傤�B
���̐l�������͂ł��܂���B
�������Ċw���̍��A���̃e���r�ԑg�̐��肢���ӎ�������������܂����B
�������l�Ԃ́u����Ƃ����i�e�Ɗ�j�v�̘b���D���ł��B
- �@���c�c���������b
- �@��c�c���ɗ��b
- �@�Ɓc�c���Șb
- �@���c�c���b
- �@���c�c�ʔ����b
����ɉ����āA
�u�p���[�X�|�b�g�v�Ƃ������b���D���ł��B
����͋t�ɂ����u�S��X�|�b�g�v�Ƃ������A
�H��̂��������ł��Ȃ�������������Ă��܂��B
�u����Ƃ����̘b�v�ɔ�ׂāA�����̘b�����Ȏ������B
����́u�{���̘b�E�^���̘b�v������ł��B
�ł������̘b�ɂł����ď��߂ċ����Ȃ���́A
�p���[�X�|�b�g��S��X�|�b�g�Ƃ������A
���M�E���M�̗ނ���ł��j�邱�Ƃ��ł��܂��B
�肢��F���A�S��X�|�b�g�Ƃ������b�����Ă��炤���тɁA
��y�^�@�̗L���𖡂키���Ƃł��B
���ׂĎ֑��A���p�Ȓ��b�ł��B
���M���M�ɘf�킳��Ȃ������A
���D�F���ɗp���̂Ȃ����O���ł��B
�i�����j ���`����
�^�@�̌ւ�
�y�����ځz
�Q�N�O�A�r�Ƃ̂��@���ɂāB
�s�̌�A�ꏏ�ɂ��������݂Ȃ���u�ǂ��炩�炱���܂������H�v
�Ƃ����˂�ƁA
���Ƒ��S�l�͊֓�����ۈ�������ĎԂŗ����Ƃ̎��B
�u�������ł��ˁv�Ɗ��S���Ă���ƁA
�e�ʂ̐l���������ƌ����܂����B
�u�������N�O�A��ӂŎO�d���܂ł��������Ƃ�����B�v
���̔N�͖��̑�w�������̂������ł��B
�d������߂�A�v�������Ĉɐ��_�{�܂ŎԂ𑖂点�܂����B
�u�P�l�ŎԂ��U���Ԃ��炢�Ƃ��āA�������ɎO�d�ɂ��āA
�����ł������āA�܂��߂��Ă��܂����B
�����т�܂�����B�v
�u��ςł����ˁc�c������ƁA�������˂��Ă����ł����H
��w�̂����Ƃ����A�悭�������^�䂩��̑��ɕ{���Ă����܂����A
�Ȃ�������֍s���Ȃ������̂ł����H
�������Ȃ甼���̎��ԂȂ̂ɁB�v
����Ƃ��̕��A�u�������͌����ڂ��Ȃ��B�v
���̑�w�ȑO�A
��̌Z��̉����̎����̎��A
���ɕ{�ł������܂������������̂ł����B
���̌�A�ǂȂ����̎��i�����̘b�ɂȂ�A
�u�����̐_�Ђ��悢�v
�u�������́������F���Ă�������v�v
�u�A��ɗ�����낤�v
�U�X�_���݂̘b�ł��肠�����Ă��܂����B
�y���Ȃ������ȁz
�e�a���l�ɂ́u�ߒQ�q���a�]�v�Ƃ����A
�P�U��́u���Ȃ��݂Ȃ����āv�Ɖr�����a�]�A���ܒ��̉̂�����܂��B
���̈��ɁA
���Ȃ������Ȃ⓹���́@�ǎ��E�g���������
�V�_�E�n�_�������߂@�m����J�Ƃ߂Ƃ�
�i������j�u���Ɣ߂������Ƃł��낤�B
�o�Ƃ̂��̂��݉Ƃ̂��̂��A
���̗ǂ�������I�сA
�V�n�̐_�X�𐒂߂Ȃ���A
�肢��F�Ƃ�����X�̂Ƃ߂Ƃ��Ă���B�v
�@���������葒�V��������A
�����ɋA�˂��A���̋�����M������̂Ƃ��Ă̂ӂ�܂������Ȃ���A
���ۂɂ́A����ȊO�̋�����M���Ă���l������A
�����Q����Ă��܂��B
���������@���ň���ɗl�̘b�������������Ă��A
���ۂɂ͕����Ă��炸�A
�肢�Ɏ����X���A�F�Ƃ��ɑ�����l�B
�O�����邱�Ƃ��Ȃ��A
�u�����͉^���ǂ����v�u�����͂��ĂȂ����v�ƁA
�����̃e���r���̉��ɂ��鐯�肢�Ɉ���J������B
�u�������̐_�͂����v������v�u�������͌����Ȃ������v�ƁA
����̊�]�Ƃ������̗~�]�̖ڂŐ_�ЁE���t�߂�l�B
�̂������ς��Ȃ��悤�ł��B
�y���߁z
���N�̊��x�́u�ւєN�v�Łu�����i���̂Ƃ݁j�v�ł��B
�����ė��N�́u�ߔN�v�A�u���߁i�Ђ̂����܁j�v�ł��B
�u���߁v�ɂ͏����Ɋւ�����M������܂��B
���߂̏����́u�C�����������v�Ƃ������M�ł��B
����Ȗ��M�������ŁA
�U�O�N�O�A�P�Q�O�N�O�̕��߂̏o�����͂ƂĂ��Ⴂ���̂������悤�ł��B
�×��u����v�������Ȃ����{�l�ɂƂ��āA
�\���\��x�͗�̌v�Z�������ő�ϖ��ɗ����܂����B
���Ȃ킿���x���킩��A
�U�O�N�O�܂łȂ�u����́����N�O�̎��v�Ƃ����ɕ����邩��ł��B
���x�̕������p�����鎖�͈������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����ǂ������Ɂu�E�E�y�E���E���v�̐����A
�P�Q��ނ̓����̃C���[�W�������Ȃ�A
�������琶�܂���̐l�Ԃ̐��i�E�l�������߂�����M�A
����ɂ��߂��������Ƃ��������̗��j�͖��ł��B
�Ȃ��P�Q�O�N�O�A1846�N�̂Ђ̂����܂̔N�A
�L����x�R�A�ΐ�Ȃǂ͏o�������������Ă��Ȃ��Ƃ����f�[�^�����邻���ł��B
�k����k����|��k�Ƃ�����y�^�@������Ȓn��ł��B
�u��y�^�@�͑��̏@�h�����q�E����ق��������߂Ă��܂����B
��y�^�@�̐M�������n��Ƃ����łȂ����ŁA
�Ђ̂����ܐ��܂�̒j����ɈႢ�����邱�Ƃ͌����œ˂��~�߂܂����B�v
�i�����w�@�y�����@�ΐ����a�@
�u���M�C�ɂ����ʋ�C����v�i�����V���R���P�Q���j���j
�E���͕����ɂƂ��čł����ލs�ׂł��B
����ǂ����M�̗͂͂�����鋰�낵��������܂��B
���M�ɘf�킳��Ȃ��C������y�^�@�ɂ͂��邱�Ƃ��A
���j��������Ă��܂��B
�i60�N�O�͂���قǑ��̒n��ƍ��͂łȂ������悤�ł����c�c�j
�y�ւ�z
�A�C�k�l�ɂ̓A�C�k���A�C�k�����Ƃ������A�C�k�̌ւ肪����܂��B
��y�^�@�̌ւ�͉����B
�u��y�^�@�̋��́i���̕��ޓ��j�v�́u�����v�Ƃ����ӏ��ɂ́A
[����]
�e�a���l�̋����ɂ݂��т���A����ɔ@���̂ݐS���A
�O�����̂��A�˂ɂ킪�g���ӂ肩����A
�Μ��Ɗ���̂����ɁA�����F���Ȃǂɂ���邱�ƂȂ��A������ӂ̐����𑗂�B
�F���ɂ����Ȃ��̂͏�y�^�@�̌ւ�ł��B
�����ƌ���̐l�ɁA�����Ă���k�ɁA
��y�^�@�̂��Ƃ�m���Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�_���݂ɗp���Ȃ���y�^�@�B
�_���݂̘b��肨���Q��̘b�ł��肠�����y�^�@�̂���k�ł��B
�i�����j ���`����
����������Ȃ�
�y�L�O���z
�g����Ƃ�������͍̂�����P�S�N�O�ɂȂ�܂��B
�����E�m���̊�b����N�ԏW�����Ċw�ԍL�������w�@�ɓ��w�����g����B
�����u�t�Ƃ��ď��߂Ċw�@�ɂ���Ă��܂����B
���̌�A�g����͓��ɐ��ɁA�l�X�ȏꏊ�ɒ����E���ɑ����^��܂��B
����ɓ��x�����m���ɂ��Ȃ��܂��B
�꓿���ɂ悭���Q�肭������悤�ɂȂ�܂����B
���N�ꌎ�̕u�̎��ł����B
�@�����n�܂邸���Ԃ�O�ɂ���ꂽ�g���v�w�B
�u���͂����k�Łc�c�v�ƁB
����̖{�����������܂����B
�{�̃^�C�g���́A
�w���s�����i����������Ȃ��j�x
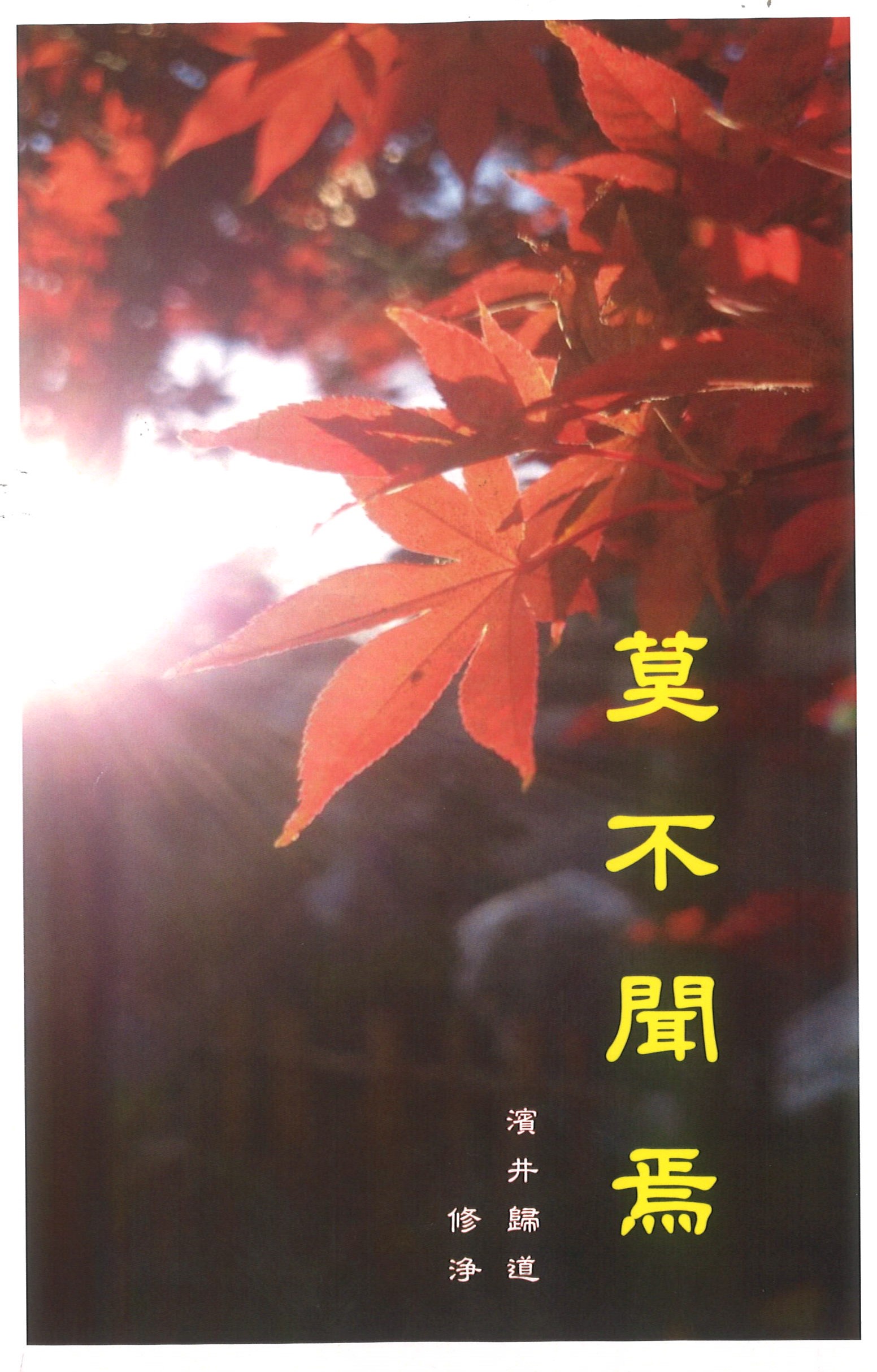
��㔪�\�N�̍��N�A
�g����̂����e��������ĔN���i25�����33����j���ނ�����̂ł����B
�����ōl����ꂽ���A
�u���O�������̂�������l�ł������̕��X�ɑ������Ă������������v�ƁA
���̍s�M���Z�̐���e�s�搶�ɂ��肢���A
�@�b�W�̋L�O���삳�ꂽ�̂ł����B
����搶���g���v�w�̊肢�ɑ�ϊ������A
���Z�������A
�s�M���Z�̎G���w�ꖡ�x��搶�̎���A
�����Ă݂����珑�����߂Ă������t�̎�ʂ̖@����A
�w����������Ȃ��x�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂ł����B
�u���̖{���ǂ�����������ɂ����Ă��������B�v
��ϊ����������k�ł����B
�w����������Ȃ��x����]�̕��A
�ǂ������A�����������B
�Z�����������Ă�������A�X�������������܂���B
���͂��������܂��B
�y���O�������Ă����ȁz
����Ȗ@�b�W�w����������Ȃ��x�̈ꕔ�����Љ���Ă��炢�܂��B
���O������������
�u�Ȃ��A�݂������A���ꂳ��̍���Ă��ꂽ�������͂��������Ȃ��B�v
�u����A���ꂳ��̍���Ă��ꂽ�������͂��������Ȃ��A�̂肭��B�v
�[�H���Ă�Ă��܂��āA���X�A�ق�Ƃ��Ɏ��X�ł����A��̓�l�̎q�����A����Ȏ��������Ȃ��炲�͂�����Ă��邱�Ƃ�����܂��B
����ȂƂ��A��e�͏Ƃꂽ�悤�Ȋ�����Ȃ��������ς��낱��Ńj�R�j�R���Ă��܂��B
�������q���̂��߂��v���č�����������q�������ŐH�ׂĂ����Ƃ����̂́A
����͂��ꂵ�����Ƃ��낤�ȂƎv���܂��B
����͂ˁA�e�̗~�ڂƌ�������܂łł����A���́A��e�̗�����������Ƃ��̋C������������ʂ��āA
�q�������ɓ͂��Ă��邱�Ƃł���Ǝv���܂��B
���t�������܂��ƁA�q������e�̍���Ă��ꂽ������H�ׂ邱�Ƃɂ���āA
���̗�����ʂ��ĕ�e�̋C�������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���܂��B
��e���A�q���̂��߂ɂƎv���č���������ɂ́A
���̕�e�̋C�������������Ă���̂ł���܂��B
��ɂ��\���܂����悤�ɁA�q�������͂��������u���������Ȃ��v�����ĐH�ׂĂ����ł͂���܂���B
�������A�e�̕�����͂����o���邾���̋C���������߂ĐH���̏��������Ă���̂ł��傤�B
���A���������\�����O�������̒ʂ�ł���ƌ����܂��B
�u�Ȃ����݂��Ԃv���邢�́u�Ȃ�܂ԁv�܂��́u�Ȃ�܂v�Ƃ���ꂪ�����������Ă��������u���O���v�́A
����ɗl���u�K�����̏�y���܂�ċA���Ă��Ă����A�����āA���肢�����炨�O���\���Ȃ������炵���Ă����B�v�Ƃ���
����ɗl�̊肢�̐S�����ׂĂ����������̂ł���܂��B
�q�����A��e�̍���Ă��ꂽ�����̖���ʂ��ĕ�e�̐S�𖡂키�悤�ɁA
���͎���\���u���O���v��ʂ��Ĉ���ɗl�́u�K����y�A���Ă�����A���O�����Ă����v�Ƃ����肢�������������������̂ł���܂��B
�H���Ƃ����܂��ƁA��N�̕u�l�ŁA���䖾�O�搶���A
�u�M�Ƃ����͕̂����邱�ƂłˁA���̂��Ƃ�P����t�͎`��i����j�Ƃ���������Ă��܂��B
����͐H���A�H�ׂ邱�Ƃł��B
���̌��������L����ł��B
�Ȃ�₢������ˁA
�H�ׂ錾�����Ƃ͂ˁA�H�ׂ邾���ł����˂�B
�o����ł������������Ƃł��B
�F����\���O�ɐH�ׂ�����o���Ă�H
�o���ĂȂ��ł���B
����A���႟��Ɗo���Ƃ���Ɖh�{�ɂȂ��ꂽ�炦�炢���Ƃ�ł��ق�܂ɁB
���ꂩ��ˁA������͂��߂Ƃ���ł������˂�B
�\���ԃg�C���s���Ăւ�l����H
�������炦�炢���Ƃ�ł��A�a�C��B
�M�ƌ����̂͂˂��A�o����ł������A���߂�ł�������ł��B
�u�Ȃ�܂ԁA�Ȃ�܂ԁv�Ƃ������O���̒��ɂˁA
�u�Ȃ�܂ԁA�Ȃ�܂ԁv�Ƃ������O���̂��̎��A
���̎��Ɂu�����A�ԈႢ�Ȃ��˂�Ȃ��A����ɗl�ꏏ�ɋ����Ă��������Ƃ���Ȃ��v�ƕ���������Ă�����ł��B
���ꂪ�M�ł��B
�ق�ł˂��A�����ň�ԑ厖�Ȃ�́A
�\���Ԃ��͂�H�ׂĂȂ��l�Ȃ��ł��傤�B
�\���ԐH�ׂւ����炢�̂��Ȃ���B
���O��������Ɠ����ł��B
���O�������������Ă����ȁB
�l�͂ˁA�u�\���Ԃ��O�����Ȃ�������S�����ʂƎv���v�ƌ����Ă��܂��B
�S������ǂȂ��Ȃ邩��������ˁA
�u����A����A�����������A�����������v�����Č����o����ł��B
���O���䑊�����ĂˁA
�u�����A����ɗl�����Ƃ��Ă��������Ă���Ȃ��A
��������Ȃ��ƌ������炢����˂�Ȃ��v�ƁA
���O���̒��Ɉ���ɗl�̂��S�����Ă���������ł��B
���˂�Ԃ����������Ă����ȁB�v
�Ƃ���������Ă���ꂽ���Ƃ��v���o���܂��B
�s�v�c�ɂ�����ɗl�̌䉏�ɋ����A�u��و���ɕ��v�Ƃ������O���̂������������������������䉏�Ɍb�܂�܂����������A
���߂āA����ɗl�̐e�S�𖡂�킹�Ă��������A���O�������������Ă��������������̂ł���Ǝv���܂��B
�i�w����������Ȃ��x77�`81�ł��j
�i�����j ���`����
�@���̌�
�y�@���Ƃ́z
�p��ł͂Q�����uFeburary�v�Ƃ����܂��B
�uTwo month�v�ł͂���܂���B
���{���a�������Ƃ������ʂȌ��̌Ăі�������܂��B
�́u�@���v�ł��B
�u���Ȃ��̒a�����́H�v
�u�@���̍���iFeburary first�j�B�v
����ȕ��ɓ������瑊��͋���邩������܂��i��j
�@���́u�����炬�v�Ɠǂ݂܂��B
�����ǂޗR���́A��ʓI�Ɂu�ߍX���i�����炬�j�v�̂悤�ł��B
�܂��܂��ߕ����X�ɒ����ތ��B
����ǂ�����Ȋ��������w���̂ł͂Ȃ��A
�~���I��葐�������錎�Łu���X�i�����炬�j�v�A
�t�Ɍ����ėz�C�������錎�Ȃ̂Łu�C�X���i�����炬�j�v�A
����Ȗ��邢����������悤�ł��B
�ł͉��̂Q�����u�@���v�Ȃ̂��B
�R��N�O�̒����̌Â������w����i�����j�x�ɁA
�u�ה@�v�i��@�ƂȂ��j�Ƃ��邻���ł��B
����ɐ��̎���́w����x���ߏ��ɂ��ƁA
�u�@�v�Ƃ́A�����ł́u���]�i�����������j�v�̈Ӗ����Ƃ��B
�u�@�ҁ@���]�V�`�B�����������o�A�@�@�R��v
�������t�̂͂��炫�ɂ������Ď��R�Ǝ��X�ɓ����o�����A
����ĂQ����̂���u�@���v�Ƃ����̂������ł��B
�y���̐S�z
�Ƃ���Ŕ@�̉��Ɂu�S�v�����Ɓu���v�ɂȂ�܂��B
���́u�v�����v�̐S�B
����l���킭�A
�u�m�v��������ɐ[���u����������v�����v�̐S�Ȃ̂������ł��B
����������u���̐S�v�B
���������x�ɂ���Ă͑�����������Ƃ͓���B
����ԈႦ�A�u�����]���đ������S�{�v�A
���́u�{�̐S�v�ɂ����܂��B
2014�N2��20���̃E�N���C�i�푈�͂܂��Ȃ��R�N�ɂȂ�܂��B
�ă��Ő푈�̏I���Ɍ��������c���n�܂�܂����B
����ށu�{�v����A����������u���v�ցB
����Ȕ@���ɂȂ��Ă��炢�������̂ł��B
�y���ω�z
�Ƃ���ŕ����ɂ����Ĕ@���Ƃ����Ο��ω�i�Q���P�T���j�ł��B
���߉ނ��܁i�߉ޔ@���j�����ςɓ���ꂽ���B
�ϔY�Ƃ��������S�𗣂ꂽ�����܂��Ō�A
���̂̎������������������A���S�ȕ����܂Ɛ���ꂽ���ł��B
��͂��͉Ԃ̉��ɂďt���Ȃ�@���̂����炬�̖]���̍��i���s�j
�����Łu�@�v�͐^�@�A��@�A�@���ȂǁA
���Ƃ�̋��n������킵�܂��B
�ł͂Ȃ����Ƃ�̕����܂��u�@���v�Ƃ����̂��B
tathA�́q���̂悤�Ɂr�q�@���Ɂr�̈ӂł���B
gata�́q�������r�AAgata�́q�����r�̈ӁB
�����ŋ����I���߂ł́AtathA+Agata�ƌ��āA
�q�i�ߋ��̕��Ɓj�����悤�ɗ����r�q�^�����痈���r�Ɖ��߂�����A
tathA+gata�ƌ��āA
�q�����悤�ɓ����悤�ɍs�����r�q�^���֕������r�ȂǂƉ��߂��Ă���B
�i��g�������T�u�@���v�̍��ځj
�u�^�@�̐��E�֗��i�����j����A�t�ɗ���ꂽ���v�A
���ꂪ�@�����܂ƌĂԈӖ��ł��B
�y�@��藈���z
���Đe�a���l�́u���ρv�ɂ��āA
�u���ρv���Ζœx�Ƃ��ӁA���ׂƂ��ӁA���y�Ƃ��ӁA��y�Ƃ��ӁA
�����Ƃ��ӁA�@�g�Ƃ��ӁA�@���Ƃ��ӁA�^�@�Ƃ��ӁA��@�Ƃ��ӁA�����Ƃ��ӁB
�������Ȃ͂��@���Ȃ�B�i�w�B�M�╶�Ӂx�A���ߔ�709�Łj
�Ɨl�X�ȈӖ������邱�Ƃ�������A
�����Ď��̂悤�Ȏ��������܂��B
�u���̔@���A���o���E�ɂ݂��݂����܂ւ�A���Ȃ͂���،Q���C�̐S�Ȃ�B
���̐S�ɐ����M�y���邪���ɁA���̐M�S���Ȃ͂������Ȃ�A�������Ȃ͂��@���Ȃ�A�@�����Ȃ͂��@�g�Ȃ�B
�@�g�͂�����Ȃ��A���������܂��܂����B
������A�����������ꂸ�A���Ƃ���������B
���̈�@��肩����������͂��āA���֖@�g�Ɛ\���䂷���������߂��āA�@����u�ƂȂ̂肽�܂ЂāA�s�v�c�̑吾����������Ă���͂ꂽ�܂Ӂc�c
�i������F
���́i����Ɂj�@���́A������Ȃ����E�̂��݂��݂ɂ܂Ŗ����킽���Ă�����B
���Ȃ킿���ׂĂ̖�������̂̐S�Ȃ̂ł���B
�i�O���҂́j���̐S�Ɂi��ɔ@��[���@����F]�́j�����M����̂ł��邩��A
���̐M�S�͂��Ȃ킿�����ł���A�����͂��Ȃ킿�@���ł���A�@���͂��Ȃ킿�@�g�ł���B
�@�g�͐F���Ȃ��A�`���Ȃ��B
������A�S�ɂ��v�����Ƃ��ł��Ȃ����A���t�ɂ��\�����Ƃ��ł��Ȃ��B
���̈�@�̐��E����`������킵�ĕ��֖@�g�Ƃ������������������A�@����F�Ɩ�����āA�v���͂��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��傢�Ȃ鐾�����������i����ɔ@���ƂȂ��j���̂ł���B�j
�^�@�̐��E�͐F���`������܂���B
�ł����畧�Ƃ͖{���A�ǂ̂悤�ɂ��\���ł��܂���B
���ꂪ�u�@�v�ł��B
����������ɂƂ́u�]�@�����i�@��藈�����j�v�A
�܂�^�@�̐��E�A�^���̐��E���炠����ł����݂ł��B
�}�v���~�����߂́u���̐S�v�Ȃ�ʎ��߂ɂ��您�����
�u���v�Ƃ����F�E�`�A
�u�����v�Ƃ������F�E���t�ƂȂ�A
�{��E�O���E�M�S�ƁA
���̒q�d�̂͂��炫�ł�����҂����݁A
���ꂪ����ɔ@���ł��B
�Q���́u�@���v�A�@�̌��ł��B
���������X�Ət�̌��ɂ��您����A�t�Ɍ������ē����o�����B
�ߍX�����Ă��ǂ��̂ŁA�������������o���������̂ł��B
�����ğ��ω����@���ł��B
���߉ޗl�̔��\�N�̂���J���ÂтA
�c���ꂽ����ɂ��܂̋����A
�@��藈�����ꂽ����ɂ��܂̂��������������A
�O���̓�����݂܂��B
��������ɂ̌��̓��ɂ����悳��A��y�ɂނ����ē����o�����O���̓��X�ł��B
�i�����j ���`����
���@��̎�
�y���ۂ��Ȃ��Ȃ�z
����̉��ځu�Ή����ہv�B
����������ȌÓ���̐r���q���Âт����ۂ�a�l�ɔ���ɍs���Ƃ������m���ł��B
�u�����Ɠa�l�͎������݂āw����ȉ������ہI�x���ē{���āA���O������̏��̖ɔ�������B�v
����������ɋ�����A�h�L�h�L���Ȃ��牮�~�ɍs�����r���q����B
�����ʼnƗ��̐l���A�u�a�l�Ɍ�����O�ɂ��炽�߂�v�Ƃ��āA
�u���[�Ȃ�قǁA�őO�X�Ō���������v���ƁA�����������オ���Ă���́B�v
����Ɛr���q�����������C���Ɍ����܂��B
�u�����A������Ƃ�����̑��ۂ͂����Ƃ͂��킹�܂���B
���ザ�ᕉ���܂����I
����������ł�����������łȂ��A
����������ł���������łȂ��A�Ȃ�Ƃ����悤�ȁA
����Ȑ��₳��������Ȃ���ł�����B
����������Ȃ炱��������A�������������������A�݂�Ȏ���Ȃ�ł�����I
�����炱�̑��ۂ��玞����Ƃ�ƁA���ۂ��Ȃ��Ȃ����Ⴄ��ł���B�v
�u�ȂB���Ȃ��Ƃ�\������B�v
���̂��Ƃ�A�D���ł��B
�i�Í����u�́u�Ή����ہv���j
�y�ϔY��z
�Ⴂ�����A�z������ŕz�������������ۂ̂��Ƃł��B
���[�A�������͔ϔY�����Ȃ�����}�v�ł��B
������u�ϔY��̖}�v�v�Ƃ����܂��B
��Ƃ����A�Z��B
�b�h�ł��ˁB
�z�������������B
���g�ɂ��Đ키���m�B��Ȃǂ��͂����Ƃ��܂��B
���l�ɁA�ϔY�������܂̐������������͂˂��Ă��܂��S�̂���悤�ł��B
��������i���Ⴏ��j�Ƃ����܂��B
�܂��z�����Ă��������B
���g�ɂ��Ă����Ă��镐�m�B
���l�ɁA�ϔY�������������ق����āA������݂������S�̂���悤�ł��B
�����遖��i���傤�܂�j�Ƃ����܂��c�c�B
������A��y�z���g�����X�A�h�o�C�X�����������܂����B
���̒��ɂłn�搶���A
�u�������́g��h�̂��Ƃ��A�ϔY���Z�ɂ݂��ĂĂ����ˁB
�ꉞ�m�F���邯��ǂ��A
�Ȃ�Ύ������̔ϔY�͊Z�̂悤�ɒE���̂Ă邱�Ƃ��ł���̂ł����H�v
�u�����A�Ⴂ�܂��B�v
�u���̎����������̌��t�c�c�m���Ă��ˁH�v
�u�c�c�����ƁB�v
�n�搶�͂₳�����u�ϔY���A�v���Љ�Ă���܂����B
�y�ϔY���A�z
�߉ނ̋��@���ق����
�V�e��F�͂˂��
�ϔY���A�̂���ɂ�
��ɂ̍O���������߂���
�i�V�e�]�j
�u�ϔY���A�v�Ƃ������t�́A
�����c�̈�l�A���a��t�́w�_���x�i���P�j�̎g�p���ł��B
���̌��t��e�a���l�́w���s�M�x�Ɉ��p����A
����ɗl�X�ȏ����Ŏg�p����܂����i���Q�j�B
�������͍߈��[�d�̔ϔY�����A���ꂽ��ԁB
�ϔY�������Ɋ���������Ԃł��B
�ϔY���ᕉ���܂���B
�������ϔY�ł��������ϔY�łȂ��A
�������ϔY�ł������ϔY�łȂ��A�Ȃ�Ƃ����悤�ȁA
����Ȑ��₳��������Ȃ��B
�������ϔY�Ȃ炱�����ϔY�A�������������������A�݂�ȔϔY�ł��B
�����炱�̎�����ϔY���Ƃ�ƁA�킽�����Ȃ��Ȃ�B
���ꂪ�u�ϔY���A�̖}�v�v�ł��B
�y�������A�z
����Ȏ��̂��߂ɁA
���߉ނ��܂��A�����c�̈�l�A�V�e��F���A
����ɂ��܂̂���y�̐��E�A����ɂ��܂̐����������߂��܂��B
����y�́u�O����\���v�Ƃ������X�̌��������A���ꂽ���E�ł��B
���̌����̐��炩���́A
�}�v���u�ϔY��f�������Ă��Ƃ��v�i���a��t�j�Ƃ������̂ł��B
���o�ɂ́u�ߏ��O���@�������A�i�������̏O�������Č����𐬏A�����ށj�v�Ƃ���܂��B
��菜���悤�̂Ȃ��ϔY�܂݂�̎��ł����Ɠ����u�������A�v�Ȃ邱�Ƃ��Ȃ����A
���ꂪ�{�萬�A�̑��͂̋����A����y�̓��ł��B
���ゾ�炯�̌Âт����ہB
����ɂ܂݂ꂽ�K���N�^�ł��B
�����������ڂł͂Ȃ��A
���̉����ēa�l�͉Ή����ۂƂ��Ƃ�A
���̑��ۂ����߂��Ƃ����̂�����u�Ή����ہv�Ƃ�������ł��B
�ォ�牺�܂ŔϔY���炯�A
���E遖��ɂ܂݂ꂽ���ł��B
����������ȔϔY�ɖڂ�w�����A
���̐��Ȃ����A�~���悤�̂Ȃ���Y�̐����āA
�����܂́u�Α��̐��E�̎҂������̋~���̂߂��āv�Ɛ����A
���̎���ۂߎ�����Ƃ����̂����o�u���ʎ��o�v�Ƃ�������ł��B
�y���@��z
�ϔY���A�̎�������ޏ�y�̓��B
����͑�ɂ����ꂽ����T�������肷�铹�ł͂���܂���B
�ł͉������邩�B
�����Ă��邱�Ƃł��B
���������Ă��邩�B
���̕��͂�ǂ�ł���͂��ł��B
���Ȃ킿�A�u�@���v�A���@�i����ڂ��j�ł��B
����ɕ��̕�����A
�u����͕�����Ȃ��v�Ƃ��u����Ȕn���ȁv�Ǝv���O�ɁA
���܂��ĕ����Ă݂܂��B
���̈���ɂ��܂̘b�A
�}�v�ɂ̓s�b�^���̘b�ł��B
���傤�NJZ�̓I�[�_�[���C�h�A
���̕��m�Ƀs�b�^�����Ă���悤�ɁB
���Ƃ�ɂ͂قlj������B
�ϔY��̖}�v�͈ꐶ�U�����܂����A
���@��̖}�v�Ƃ��Đ��U�A
���O���������Ă����܂��B
�i���P�j
�u�}�v�l����ĔϔY���A������܂����̏�y�ɐ����邱�Ƃ�A
�O�E�̌q�ƁA�L�킶�Č������B���Ȃ͂�����ϔY��f�������ğ��ϕ��A
���Â��v�c���ׂ���B�v
�i���Q�j
�E�ϔY���A�̖}�v�A�����ߑ��̌Q�G�A��������̐S�s���l��A���̎��ɑ�搳���ڂ̐��ɓ���Ȃ�B�i�؊��j
�E�ϔY���A�̖}�v�A�����ߑ��̌Q�G�A�����̐S�s���l����Ȃ͂���搳����ڂɏZ���B�i�w��y��������x�j
�E�ϔY���A�̖}�v�l�A�M�S�J��������Ȃ͂��E���l�A�������Ȃ͂����ςȂ�Əؒm���B�i�O�f���j
�E�ϔY���A����}�v�l�A�ϔY��f�������ğ��ςA���Ȃ͂�������y���R�̓��Ȃ�B�i�w���o����x�j
�E�ϔY���A�̂���ɂ́@��ɂ̍O���������߂��ށi���m�a�]�j
�E�ϔY���A�̂��炪�@���͂̐M�Ƃׂ̂��܂Ӂi�O�f���j
�E�ϔY���A�̖}�v�A���̐S���ɏƂ炳��܂�点�ĐM�S���삷�B�M�S���삷����ɐ����ڂ̐��ɏZ���B�i������j
�i�����j ���`����
�����
�y�M���b�Ƃ����z
����A���m��ʕ����炨�莆�����炢�܂����B
���߂Ă��ւ肵�܂��B
15�N���炢�O�ɐV���̐܂荞�݃`���V�ɐ꓿���l�̍L���������Ă��܂����B
�u���ꏏ�ɐe�a���l�̋������w�т܂��H�v�Ƃ������e�������Ǝv���܂��B
���ꂩ�牽�x�����@�b�����߂�
������̂����ɂ��Q�肵����������܂��B
���́A���N��10���ɋ`����S�����܂����B
���ꂩ��ꌎ�o�������A�x��ł��܂��Ɠ��̒���
�u
�{�ʼn̎��ׂ��u�M���b�v�Ƃ��܂����B
�u�g�ɂ��Ă��v�Ƃ�
�u�ق˂��������Ă��v�Ƃ�����܂����B
�u����ł������A�~�_�l�Ɋ��ӂ��Ȃ����B�v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��傤���H
���w���ɂ�����悤�ɂ₳����
�u�����]�v�̈Ӗ��������Ă��������܂��H
�@�b�����l�����炱���̎���ł��B
�ƂĂ��L����莆�ł����B
�y���g�̊�сz
�@���莆���肪�Ƃ��������܂����B
�@���āu�����]�v�̉̎��ɂ��ĕs�R������Ƃ̎��A���m�������܂����B������́A
�u�g�ɂ��Ă��v�Ƃ��u�����������Ă��v�Ƃ�����܂����B�u����ł������A�~�_�l�Ɋ��ӂ��Ȃ����B�v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��傤���H
�@�܂������]�ɂ��ď����q�ׂ܂��B
�@�����]�́u�̂�Ȃ��@���͂Ȃ��v�Ƃ������A��y�^�@�ōł��L���ȕ����]�̂ł��B
�@���̉̎��͌��X�A�e�a���l������� �a�] �̈��ł��B
�@�a�]�͓������s�����u���ܒ��̉́v�ł��B���悻7������5�����̒��q�ō��̂ŁA�Ⴆ�u�t�̂����́i7�j���c��i5�j��v�i�ԁj�A�u�l���y�����i8�j������邳�i5�j��v�i���ˉ���j�A�܂��u����������́i7�j�����ӂ����i5�j�v�i���Ƃ���ۂہj�Ƃ��������q�݂��U�̎������ܒ��ł��B
�@�e�a���l�͘a�]���������삳��܂����B���o�̓����������{��̉̂ɂ��邱�ƂŁA�������ł��g�߂ɂ��Ă��炨���Ƃ����Ӑ}���������̂�������܂���B
�@����ǂ�����Ȓ��A���l�����g�̎v���A���~���ɂł�������т��������r�����a�]���A�u�����]�v�̉̎��ł��B
�@����߂̉����́�i�ɂ�炢�����Ђ̂���ǂ��́j
�g�ɂ��Ă��ׂ���i�݂����ɂ��Ă��ق����ׂ��j
�t��m���̉�������i�����タ�����̂���ǂ����j
�ق˂��������Ă��ӂ��ׂ���i�ق˂��������Ă����Ⴗ�ׂ��j
�u���g�̊�т�\�������́v�A�������|�C���g�ł��B���l�������������e�ł͂���܂���B
�@����Ȑe�a���l�̐S�����݂Ƃ�A�������e�X�����g�̊�т̕\���Ƃ��ĉ̂����߂ɂł����̂������]�́u�����]�v�ł��B
�@�ł͂�����ɂ��������܂��B
�@�u�g�ɂ��Ă��v�u�����������Ă��v�Ƃ͔��ɋɒ[�Ȍ������ł����A����́u����ɂ��܂̂��~���ɂ����������҂݂͂ȁq�n���o�[�O�r�ɂȂ�v�Ƃ����b�ł͂���܂���B�u���ʋC�Łv�Ƃ��u���ʂ܂Łv�A�܂��Ă�u������v�Ƃ����Ӗ��ł�����܂���B
�@���Ƃ��A���̍Ȃ͂悭�����������̂�H�ׂ��Ƃ��u��������ł��ǂ��I�v�ƌ����܂��B�{���Ɏ���ł��ǂ��킯�ł͂���܂���B�ł��R�ł͂Ȃ��̂ł��B���̔��������A�����H�ׂ������̊������ō��ɕ\�������������߂ɁA���̂悤�Ȍ������ɂȂ�̂ł��B
�@���Ȃ݂Ɏ��̏ꍇ�A�傢�Ɋ����������̌��Ȃ́u���ɂȂɂ�����Ȃ��I�v�ł����A�{���Ɂu���ɂȂɂ�����Ȃ��v�̂����u�����ƁA�炢���̂�����܂��B
�@���Ɂu�ׂ��v�u�ӂ��ׂ��v�Ƃ́A�l�܂鏊�u����i���Ӂj�������ɂ͂���܂���v�Ƃ����Ӗ��ł��B���̂���i���Ӂj�ł����A���낢�날���Ă��A��͂�u���O���v�����S�ł��B�u��و���ɕ��v�ƌ��ɂ���s�ׂ��͂����āu����v�͂���܂���B
�@�u�ׂ��v�u�ӂ��ׂ��v�́u�`�ׂ��v�́u�i���l����́j���߁v�̈Ӗ��ł͂���܂���B�����̋C�����E�ӎu�ł��B��قǑ�ȃ|�C���g�ƌ����܂������A���̘a�]�́u���g�̊�т�\�������́v�ł��B�e�a���l���e�a���l�ɁA���������g�Ɍ�����������̂ł��B�u�����́`���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�A�����Ƃ����u�`�����ɂ͂���Ȃ��v�Ƃ����̂��{���ł��B
�@����߂̉����́i����ɂ��܂̂��~���́j
�g�ɂ��Ă��ׂ��i����ȏ�Ȃ���тł��j
�t��m���̉������i���߉ނ��܂⑽�����L���̕��X�ɂ��j
�ق˂��������Ă��ӂ��ׂ��i�����\�����ɂ͂���܂���B�j
�@�u�t��v�͕����k�S���̎t���ł���A�����ł��邨�߉ނ��܂ł��B
�@�u�m���v�͑P�m���i�������E�������j�Ƃ����āA���������ɓ����Ă��������������̕��X�̎��B�������V�������ł����ɂł������Ȃ�A���̖S���������ɂƂ��đP�m���Ƃ�����ł��傤�B
�@����Ԃ��悤�ł����A�����]�͖S���Ȃ������ɂ����鐺�����ł͂���܂���B�����g�����������Ĉ�l�ɂ͂��Ȃ��u�@����߂̉����v�Ƃ����~���ɂł�������т̕\���ł��B
�@���A�ڂ��J�������A�q�d�̊�̂Ђ炩�ꂽ�����܂ƈꏏ�ł��B
�@��l�ɂސg�̂������鎞�A���ɐS��ɂ߂Ă�����������ꏏ�ł��B
�@�����̐l�����ӂ肩����A�Ȃ����A�܂��鎞�A���ɗ܂����ڂ��Ă���������A�u���̂��Ȃ��̐l�����]�ւƗ��Ƃ��Ȃ����߂Ɏ��͕��ɂȂ�v�Ɛ���ꂽ���ƈꏏ�ł��B
�@�u����ł��������ӂ���v�ƎƂ߂�̂ł͂Ȃ��A�u���̔ϔY�܂݂�̖}�v�̎��́A���A����ł����A���Ƃ��S�N��A��N�������炸���ӂ����ɂ͂���Ȃ����̑傫�Ȃ��������������܂����B���O�����������ɂ͂���܂���ł����B�v����Ȗ��킢���̂��Ċy���������]�ł��B
�c�c�ł͂��ł�����ɂ��܂Ɋ��ӂ����O�����Ă��邩�B����Ȏ��͂��肦�܂���B�ϔY�܂݂�̎��́A�g�̂��ɂ����A��ꂽ���A�����Ă��鎞�A���ӂ̎v���Ȃ�Đ������ł��܂��B�ł�����ȔϔY�܂݂�̎��ƌ��������̂�����ɂ��܂ł���A�̂́u���O���̋~���v�u�������̋~���v�ł��B�n�b�Ɖ�ɂ����������A���悢�擪��������A���O�����������Ƃł��B
�@�����A���ɏ�y�^�@�́u���͂̋����v�͌�����ꂪ���ł��B�����͂��낢��ł��傤���A���̈�ɁA�l�͗ǂ����������S���Ȃ������̎����C�ɂȂ��āA�������u�����Ɓi���̂��߂ɂ��鋳���j�v�u�����̏u�Ԃ̖��v�Ƃ͎~�߂ɂ����悤�ł��B
�@�ǂ�Ȑl���ŏ��́A�u���o�Ƃ��������āA�����Ƃ��������āA���d�����āA�S���Ȃ����l�̂��߂ɂ���̂��v�Ƃ�������ρE�v�����݂�����܂��i���̎q�ǂ��B�������ł��j�B���̎v�����݂����邩����A�ǂꂾ���@�b���������Ă���y�^�@�̖��킢�͕�����܂���B����ǂ����̎v�����݂��ł��ӂ����̂�����ς�u�������v�ł��B
�@�̐l���Ȃ�������ɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B��������ʂ��Ď����g���u�@����߂̉����v�ɂł������������A���ǁA�̐l�ɂƂ��ĉ����̊�тƂȂ�̂ł��B���̂悤�Ɏ����g���u�������v�ŋ�����Ă��܂��B
�@�܂����ł������₨�҂����Ă���܂��B
����
�i�����j ���`����
���݂̂�Ɂ@�݂݂����܂�
�y�J��r���Y�z
�@���Â�̂Ƃ��ɂ��O�k�����ł�
�@�����ӂ��������Ђ�
�@�˂ɖ�ɂ�O���ׂ�
�i����ɕ��̖{��̂͂��炫���Ȃ���A�͂����Ă��O�k���E[�������E]���o�邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
���̂�����[���v���A��Ɉ���ɕ��̖������̂��邪�悢�B�j
�O�k
�@��y
�@�{�t�߉ނ̂�����Ȃ�
�@
�i�w���m�a�]�x�P���]���j
�i�O�k���E�ł̉ʂĂ��Ȃ������Ԃ̋���̂āA��y�ł��Ƃ��Ɗ����邱�Ƃ��ł���̂́A�ߑ��̂��͂ɂ��̂ł���B
�������̑傢�Ȃ鎜�߂̉��ɕ邪�悢�B�j
���N���������@�b���f�ڂ����Ă��������܂��B
�y�J��r���Y�z
��N11��13���A�J��r���Y���S���Ȃ��܂����B
���{���\����A�����I���l�E�J��r���Y�B
�݊w���̏Ռ��I�ȏ������W�w��\�����N�̌ǓƁx�B
���ꂩ��70�N�ԁA���ɏo�������W�E���I�W��80���ȏ�A
��������i��2000�قǂ��邻���ł��B
�u���̃����[�v���A�����̎������ȏ��Ɍf�ڂ���A
���������ȁu�N���[�̊G�{�v�i�O�P�W��ȁj���A�������̍쎌������܂��B
�q�ǂ������̍�i�������A
���w�����x��A�G�{�w�������������x�w����݂͂̂̂҂��x�ȂǁA
�u�q�ǂ������̂��Ƃ�[���L���Ɍ@��N�����d���v������܂����B
�@�@������
���������
����������
�Ƃ��Ă����Ă�
�����ςȂ��ς�����
�����ςȂ��ς����ς�����
��������������
�y�������Ƃ����т̎�����������܂��B
�X�k�[�s�[�̏o�閟��w�s�[�i�b�c�x��|�������̂��J�삳��B
�q�ǂ��̍��ǂw�}�U�[�E�O�[�X�̂����x��w�X�C�~�[�x���J��r���Y��ł����B
�y�����z
����ȒJ��r���Y�����49�������N�̑�A���ł����B
�����ŏ����̖{���ŒJ��r���Y����̓���𗬂��܂����B
������26�N�O�A����10�N6��25���A
�꓿���u���a���v�ł̃R���T�[�g�u���y�Ǝ��̘N�ǂ̗[�ׁ@�`�݂݂����܂��`�v�̉f���ł��B
�o���͒J��r���Y����Ƒ��q���삳��̉��y�O���[�v�u�c�h�u�`�v�B
�g���̂r���j�搶���L�^���������܂����B
�R���T�[�g�͒J�삳���̘N�ǂ��A
�����Ăc�h�u�`���J�삳��̎��ɋȂ����ĉ��t�B
�J�삳��́A�`���Ɂu���̂ЂƂ��������Ƃ��v�A
���Ɂu�ق��Ƃ��v�u���̂��v�i���Ƃ����т����j�Ƃ������y���������A
����Ɂu�n���ւ̃s�N�j�b�N�v�u�n���̋q�v�A�u���낤�Ƃ��邱�Ƃ́v�B
�����čŌ�͑s��Ȏ��u�݂݂����܂��v�̂��悻5���Ԃ̘N�ǂł����B
�݂݂����܂�
���̂���
���܂����
�݂݂����܂�
�݂݂����܂�
������
�Â��Ă����Ƃ������
�������Ƃ�
�݂݂����܂�
�߂��ނ�
�݂݂����܂�
�n�C�q�[���̂�����
�Ȃ����̂ǂ��ǂ�
�ۂ�����̂ۂ��ۂ�
�݂݂����܂�
�ق��̂�����
���݂����̂�����������
������̂���
�݂݂����܂�
�c�c�i�������������j
���v���Ζ��̂悤�Ȏ��Ԃł����B
�u���Ƃ̂��鏊�Ȃ�ǂ��ɂł��r���Y������v�i�F�l�E��������Y�j
�N�ǂ̖���ł��莍�̃{�N�V���O���E���C�g������2��ڃ`�����s�I���B
�S�r�A�g���̎��̂̍쎌�ƁB
�c�c�肪����܂���B
�u���Ƃv�Ƌ��ɕ��݁A
�u���Ƃv�̂��ɂ͂���������A
����ȕ��ł����B
�y�݂݂����܂��z
�R���T�[�g�̎n�܂�O�̈��A�ŁA
�O�Z�E�́u�݂݂����܂��́A�܂�ő�a���t�ŏ����ꂽ���o�ł��v�Ɛ������܂����B
���̗��R�͂܂��A���o�̖`���ł��B
���o�͕K���Ƃ����Ă����قǁu�@���䕷�i�����̂��Ƃ���ꕷ���j�v�Ŏn�܂�܂��B
�����āA��������u�����l��̖@��v�Ƃ�����悤�ɁA
�c��Ȃ��߉ނ��܂̋�����������܂��B
�������͎�������Ȃ͂��炢�����āA�݂݂����܂���̂ł��B
����Ȃ��o�̒��ɁA
�e�a���l�����ǂ���Ƃ��ꂽ���{�o�T�w�������ʎ��o�x������܂��B
�l�X�̑����A�n���̗��j�̉��A
�����̉ߋ��̉��A�l�X�ȏo�����A
�y�������A�߂������A�h�����A��т̐��A
����߂��̂����̍��̐��A
�����̏���̂����炬�̐��B
����Ȉ��̉��ɁA
���������̊��ѐ����䂫�킽���Ă���Ɩ����ꂽ�e�a���l�ł��B
�����̐��납��F���̂Ƃǂ낫�܂ŁA
���̂��̂��Ɋւ�鉹��Ɏ������܂��Ȃ���A
�����ɂ��݂��@���̊肢�A�~���̐��ɂ݂݂����܂��܂��B
�u���ꂪ���o�A���߉ޗl�����̐��ɂ����ꂽ�ړI�ł����v�ƁA
�e�a���l�͂����M��ɐ�����܂��B
�����Ď������͉�������̂��B
�������ł��B
�u
�����܂̐��ɂ݂݂����܂������ł��B
�V�N���n�܂�܂����B
���N����N�ԁA
����̐l�����v���A
���@�̐l�����d�˂A
��ɂ̖������̂��B
���������y�̓���i��ł����܂��B
�J��r���Y����̂悤�ȁA
�u���Ƃv�̂��ɂ��������镧���܂�
�ӂꂠ���Ă��������Ǝv���܂��B
���u�݂݂����܂��v��4�N�O�́u�Z�E������v�ł��Љ���Ă��炢�܂����B
���@�R���T�[�g�̗l�q�̈ꕔ�������ł��B
�i�����j ���`����
�@�b2025�֘A�y�[�W
- �@�b2024
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2023
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2022
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2021
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2020
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2019
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2018
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2017
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2016
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2015
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2014
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2013
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2012
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2011
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2010
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2009
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2008
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@�b2007
- �悤�����꓿���ւ��Q�肭�������܂����B �꓿���͊⍑�s�ʒÂɂ����y�^�@�{�莛�h�i���{�莛�j�̎��@�ł��B �ǂ�����������肭�낢�ł��������B
- �@��365��
- 365���A�����Ⴄ�@�b���ǂ߂܂��B

![���]�J�����_�[202509](../../img/���]�J�����_�[202509.png)